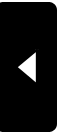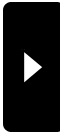秋の霧訪山を歩く
10:00 プールの友達と、塩尻市下西条の登り口に行きます。
この八沢川の流域を、地元の人たちが整備し大切にしています。
案内板を大きくして見てね。

少し歩いて、「たまらずの池」を覗いてみます。
今の時期は、名前のとおりほとんど水がありません。

明るい日差しを浴びて、良く整備された登山道を登ります。

11:20 尾根に出ました。 今日は、霧訪山へ直行します。

少し行くと、直登する男坂と迂回路の女坂があり、
カタクリの花の時期には楽しめます。
女坂を通って、 11:40 山頂(1305.4m)に到着です。
山頂からは、諏訪湖の向うに八ヶ岳・西に穂高岳と素晴らしい眺めです。


山頂で会った人は、地元のご夫婦と北小野方向から来た男性の3人でした。
偶然でしたが、このご夫婦とは知り合いだったので、久しぶりの邂逅が嬉しかったです。
ゆっくり昼食をとり、12:45 西方を周って下りることにします。
まもなく、案内標識があります。

この道は、前に「山歩きの会」で教えてもらったルートです。
尾根道の下り・登りですが、途中に1本だけブナがありました。
根元から数本に分かれた木ですが、付近に他のブナは見えません。

急な登りを詰めると、「えぼし」です。 13:07です。

針葉樹では、アカマツとカラマツが多いのですが、コメツガもあります。
この大きな鉄塔は、登るときに見た鉄塔のすぐ西側の鉄塔です。


この道は尾根を歩くルートで、右側は市有林・左は宗賀の山で
マツタケ山として入山禁止になっています。

13:35 尾沢峠に着きました。

このまま歩き続けて、たまらずの池に14:08 駐車場所に14:15到着です。
登りが 1時間40分、下りが 1時間30分でした。
今回は11月にしては暖かく、穏やかな陽気に恵まれた里山歩きになりました。
この八沢川の流域を、地元の人たちが整備し大切にしています。
案内板を大きくして見てね。
少し歩いて、「たまらずの池」を覗いてみます。
今の時期は、名前のとおりほとんど水がありません。
明るい日差しを浴びて、良く整備された登山道を登ります。
11:20 尾根に出ました。 今日は、霧訪山へ直行します。
少し行くと、直登する男坂と迂回路の女坂があり、
カタクリの花の時期には楽しめます。
女坂を通って、 11:40 山頂(1305.4m)に到着です。
山頂からは、諏訪湖の向うに八ヶ岳・西に穂高岳と素晴らしい眺めです。
山頂で会った人は、地元のご夫婦と北小野方向から来た男性の3人でした。
偶然でしたが、このご夫婦とは知り合いだったので、久しぶりの邂逅が嬉しかったです。
ゆっくり昼食をとり、12:45 西方を周って下りることにします。
まもなく、案内標識があります。
この道は、前に「山歩きの会」で教えてもらったルートです。
尾根道の下り・登りですが、途中に1本だけブナがありました。
根元から数本に分かれた木ですが、付近に他のブナは見えません。
急な登りを詰めると、「えぼし」です。 13:07です。
針葉樹では、アカマツとカラマツが多いのですが、コメツガもあります。
この大きな鉄塔は、登るときに見た鉄塔のすぐ西側の鉄塔です。
この道は尾根を歩くルートで、右側は市有林・左は宗賀の山で
マツタケ山として入山禁止になっています。
13:35 尾沢峠に着きました。
このまま歩き続けて、たまらずの池に14:08 駐車場所に14:15到着です。
登りが 1時間40分、下りが 1時間30分でした。
今回は11月にしては暖かく、穏やかな陽気に恵まれた里山歩きになりました。
木曽かぶの漬物
親戚から木曽カブを沢山分けてもらったので、さっそく漬けます。
まず、外水道でざっと洗います。

もう一度洗ってから、早く食べる分は切り漬けにします。

最初に、少なめの塩で、塩漬けにします。

切り漬け10kg、丸のままが20kgです。
重しをして、水が上がるのを待ちます。

切り漬けは、半日ほどで水があがりますので、塩水をきって酢と砂糖で
漬けこみます。

私の分担は、洗ったり・重しを用意したりで、もっぱら下働きです。
3日ほどで、良い色になりますので、さっそく試食してみます。
子供たちにもあげますが、食べる時の主役は? もちろん私です。

干し柿づくりも、この時期です。

今年は、柿の当たり年のようで、「道の駅」で買ったり・人に頂いたりで、
3回目の皮むきです。
まず、外水道でざっと洗います。
もう一度洗ってから、早く食べる分は切り漬けにします。
最初に、少なめの塩で、塩漬けにします。
切り漬け10kg、丸のままが20kgです。
重しをして、水が上がるのを待ちます。
切り漬けは、半日ほどで水があがりますので、塩水をきって酢と砂糖で
漬けこみます。
私の分担は、洗ったり・重しを用意したりで、もっぱら下働きです。
3日ほどで、良い色になりますので、さっそく試食してみます。

子供たちにもあげますが、食べる時の主役は? もちろん私です。
干し柿づくりも、この時期です。
今年は、柿の当たり年のようで、「道の駅」で買ったり・人に頂いたりで、
3回目の皮むきです。
新そばを味わう
新そばの美味しい季節になりました。
「お昼に打つからおいで。」と、なっちゃんの家をお誘いしました。
「北小野で栽培している。」と言う、テヅカライスの粉を用意し、
みんなが来る前に打ち始めます。

そば粉500gと400gで2回に分けて打ちます。
延ばした形が少しおかしいですが、気にせず、たたんで切ります。


家内がてんぷらを揚げ、なっちゃん達がそばを茹でたりして準備完了です。

子供も入れて6人ですので、茹であがる順にいただきます。
大根おろしは、今年初めて作った穂高の牧大根が良いみたいです。
食後、ユウ君とキャッチボールをし、雨が降ってきたので将棋をしていると、
お菓子作りが始まりました。
ハンドミキサーで、ケーキのスポンジづくりの開始です。

あやちゃんは、底に敷くクッキングシートを作ります。

オーブンで焼いて、スポンジができ上がり、良い香りが漂います。

いよいよ、ケーキに塗るチョコレートクリームをホイップします。
ユウ君も見学です。

いろんな手が出てきて、みんなで好きなようにクリームを塗っています。

ココアを振りかけて、 いただきま~す。



ティータイムは、、コーヒーに手作りケーキです。
美味しいですが、年寄りにはカロリーオーバーかも?
「お昼に打つからおいで。」と、なっちゃんの家をお誘いしました。
「北小野で栽培している。」と言う、テヅカライスの粉を用意し、
みんなが来る前に打ち始めます。
そば粉500gと400gで2回に分けて打ちます。
延ばした形が少しおかしいですが、気にせず、たたんで切ります。
家内がてんぷらを揚げ、なっちゃん達がそばを茹でたりして準備完了です。
子供も入れて6人ですので、茹であがる順にいただきます。
大根おろしは、今年初めて作った穂高の牧大根が良いみたいです。

食後、ユウ君とキャッチボールをし、雨が降ってきたので将棋をしていると、
お菓子作りが始まりました。
ハンドミキサーで、ケーキのスポンジづくりの開始です。
あやちゃんは、底に敷くクッキングシートを作ります。
オーブンで焼いて、スポンジができ上がり、良い香りが漂います。
いよいよ、ケーキに塗るチョコレートクリームをホイップします。
ユウ君も見学です。
いろんな手が出てきて、みんなで好きなようにクリームを塗っています。
ココアを振りかけて、 いただきま~す。
ティータイムは、、コーヒーに手作りケーキです。
美味しいですが、年寄りにはカロリーオーバーかも?

牛伏川の石積み堰堤
厄除けの「牛伏寺」の南を流れ下る牛伏川の石積み堰堤を見に行きました。
お寺は、ごふくじ。 川は、うしぶせがわと読むのです。
駐車場を出ると、すぐ階段状の流れが目に飛び込んできます。
説明板にフランス式階段工とあります。

「大正5~7年に作られ、延長141mの間に19段の階段状の流路がある。」
と、書かれています。
岸辺の草はきれいに刈られ、流れの中も清々しい感じです。
いま10:30ですが、全体の配置図面を見て、
できたら一番上流の地獄谷まで行こうと思います。(クリックしてね。)

前から、見たいと思っていた場所なので、
説明板を読んだり、写真を撮ったりしながらゆっくり登っていきます。
右岸にキャンプ場があります。 この辺もきれいに整備されてます。
流れに飛び石を沈めてあるので、容易に川を渡ることができます。

これは、根止石積堰堤と言って、明治18~22年に作られた施設だそうです。

11:00です。 木の名前が分かりませんが、食べられる実でしょうか?

いろいろな木に説明板が付けられています。
ミズキ、カンボク、マユミ、ズミ、エンコウカエデ、ハリエンジュなど。
なかでも、ハリエンジュ(ニセアカシア)は建設時に植えられたものですが、
大きくなった木が倒れるとき、地盤を崩壊させるという害があるので、
少しずつ取り除いて元々あった樹木に変えているそうです。
この辺りから、川幅が狭くなり、車道は無くなりますが、やはりきれいに整備されています。


さらに登ります。 ここまで約1時間です。


ニセアカシアの木に、巻き枯らしの処理をしてあります。
水量は少なく、歩道は木の階段で、シカの足跡が多く見られます。


11:45 地獄谷の堰堤に着きました。
この上流は堰堤が土砂に埋もれているそうです。右の写真がそうです。


見晴らしの良いところに出ました。
手前が松本カントリー、西方の山々は雲で見えません。

12:00です。 お昼を持ってこなかったので、帰ることにします。
来たときとは違う道を帰ろうと、石切り場と言うところまで登ってみます。
明るい広葉樹の林に、道順を示す青や赤のテープがあります。

向うに、赤いものが翻っていると思い、近づくと鯉のぼりです。

13:00 ここが石切り場です。
展望がよく、右下には中山霊園が見えます。
斜め左下に降りていくと、尾根道のようになってきたので、さらに降ります。


途中に、「牛伏寺~鉢伏山」の道標があり、少し下に獣防止の柵があります。
柵に沿って下りますが、結局この道は柵の内側に入るのです。 14:15です。

柵内の道を、どんどん下ります。
向うが明るくなって、最後の急坂を下りるとダム上の駐車場です。
道標があって、「鉢伏山 5.7km」とありました。
まだ、紅葉には早いダムの写真です。

ここから、牛伏川の駐車場まで歩きます。
14:40到着でしたので、4時間ほど歩いたことになります。
また、来たいと思います。
明治・大正の石積み施設が、今も健在でこの谷間を守っているところを。
石積み施設が、山や川に融和した独特な景観に会うために。
お寺は、ごふくじ。 川は、うしぶせがわと読むのです。
駐車場を出ると、すぐ階段状の流れが目に飛び込んできます。
説明板にフランス式階段工とあります。
「大正5~7年に作られ、延長141mの間に19段の階段状の流路がある。」
と、書かれています。
岸辺の草はきれいに刈られ、流れの中も清々しい感じです。
いま10:30ですが、全体の配置図面を見て、
できたら一番上流の地獄谷まで行こうと思います。(クリックしてね。)
前から、見たいと思っていた場所なので、
説明板を読んだり、写真を撮ったりしながらゆっくり登っていきます。
右岸にキャンプ場があります。 この辺もきれいに整備されてます。
流れに飛び石を沈めてあるので、容易に川を渡ることができます。
これは、根止石積堰堤と言って、明治18~22年に作られた施設だそうです。
11:00です。 木の名前が分かりませんが、食べられる実でしょうか?
いろいろな木に説明板が付けられています。
ミズキ、カンボク、マユミ、ズミ、エンコウカエデ、ハリエンジュなど。
なかでも、ハリエンジュ(ニセアカシア)は建設時に植えられたものですが、
大きくなった木が倒れるとき、地盤を崩壊させるという害があるので、
少しずつ取り除いて元々あった樹木に変えているそうです。
この辺りから、川幅が狭くなり、車道は無くなりますが、やはりきれいに整備されています。
さらに登ります。 ここまで約1時間です。
ニセアカシアの木に、巻き枯らしの処理をしてあります。
水量は少なく、歩道は木の階段で、シカの足跡が多く見られます。
11:45 地獄谷の堰堤に着きました。
この上流は堰堤が土砂に埋もれているそうです。右の写真がそうです。
見晴らしの良いところに出ました。
手前が松本カントリー、西方の山々は雲で見えません。
12:00です。 お昼を持ってこなかったので、帰ることにします。
来たときとは違う道を帰ろうと、石切り場と言うところまで登ってみます。
明るい広葉樹の林に、道順を示す青や赤のテープがあります。
向うに、赤いものが翻っていると思い、近づくと鯉のぼりです。

13:00 ここが石切り場です。
展望がよく、右下には中山霊園が見えます。
斜め左下に降りていくと、尾根道のようになってきたので、さらに降ります。
途中に、「牛伏寺~鉢伏山」の道標があり、少し下に獣防止の柵があります。
柵に沿って下りますが、結局この道は柵の内側に入るのです。 14:15です。
柵内の道を、どんどん下ります。
向うが明るくなって、最後の急坂を下りるとダム上の駐車場です。
道標があって、「鉢伏山 5.7km」とありました。
まだ、紅葉には早いダムの写真です。
ここから、牛伏川の駐車場まで歩きます。
14:40到着でしたので、4時間ほど歩いたことになります。
また、来たいと思います。
明治・大正の石積み施設が、今も健在でこの谷間を守っているところを。
石積み施設が、山や川に融和した独特な景観に会うために。
秋の野菜畑
シュウ坊が来たので、さつまいも掘りをします。
あらかじめ、ツルや葉を取り除いておいたので手でも掘れます。

でも、大きい。 「うーん おっきい~。」


初めてサツマイモを作ってみましたが、こんなに大きくなるとは。
ついでに、残ったカボチャも収穫します。

細長い形や、円いのなど、いろいろです。 味は、いかがでしょうか?
ほかの畑で、落花生を掘ってみます。


今年は、雨が少なかったせいか未熟のサヤが多いようです。
茹でて食べると、美味しくて手が止まりません。
ニンジンのおろ抜きや小松菜も採ります。

家へ帰ると、すぐ自転車です。 お父さんも一緒に走ります。

大きくなりすぎたサツマイモですが、輪切りにしてレンジでチンして食べてみたら、ホクホクして意外と美味しかったです。
家内からは「あまり沢山とれなくてよかったね。」でした。
あらかじめ、ツルや葉を取り除いておいたので手でも掘れます。
でも、大きい。 「うーん おっきい~。」
初めてサツマイモを作ってみましたが、こんなに大きくなるとは。

ついでに、残ったカボチャも収穫します。
細長い形や、円いのなど、いろいろです。 味は、いかがでしょうか?
ほかの畑で、落花生を掘ってみます。
今年は、雨が少なかったせいか未熟のサヤが多いようです。
茹でて食べると、美味しくて手が止まりません。
ニンジンのおろ抜きや小松菜も採ります。
家へ帰ると、すぐ自転車です。 お父さんも一緒に走ります。
大きくなりすぎたサツマイモですが、輪切りにしてレンジでチンして食べてみたら、ホクホクして意外と美味しかったです。
家内からは「あまり沢山とれなくてよかったね。」でした。

秋の爺ケ岳に登る
山好きな友達に誘われて、初めての爺ケ岳です。
6:30 扇沢駅近く、籠川沿いにある登山口を出発。
7:20 急な坂を登ると、「八ッ見ベンチ」とあり、素晴らしい眺望。
カメラ片手の女性に聞くと、「正面が針ノ木岳・左手に蓮華が見える。」と教えていただく。

さらに進んで、7:40 「駅見坂」とある場所で、左に蓮華岳、右に針ノ木岳をパチリ。
下方には、扇沢の駐車場が見えます。

安曇野から見ると、針ノ木岳は蓮華岳の陰に隠れているようです。
7:50 彼方の稜線に、赤い屋根の建物が、「種池山荘」とのこと。
(クリックして大きくしてね。)

道沿いには、赤い実をつけたゴゼンタチバナ。

8:30 「一枚岩」を通過、 まもなく鮮やかな紅葉が目につくようになります。

9:30 「ガレ場」を通過。
10:00 種池山荘に到着ですが、この辺りから霧が濃くなってきます。

降りてきた人からは、「稜線は風が強く、寒い。」と、教えられる。
予備のチョッキに手袋、寒さよけの雨具を着込んで出発です。
稜線はハイマツ帯です。
霧が無ければ、周囲の山々が見えると思うのですが、黙々と進むだけです。

10:50 降りてきた人から、「少し上に、ライチョウがいますよ。」と教えていただく。
いました。3羽見えます。 家族でしょうか?
思いがけない「霧の贈り物」です。

気を良くして、歩くうちに霧も少しずつ晴れてくるようです。
11:05 爺ケ岳中峰の標識です。

11:20 山頂(2670m)です。

霧の晴れ間に撮った「針ノ木岳」と頭だけの「鹿島槍」です。


南峰(2660m)への道です。 帰り道に登ってみます。

山頂でゆっくりしていたので、12:30出発です。
来る時は、気づかなかった「シラタマノキ」です。

稜線では、チングルマ・ガンコウラン・シャクナゲなどが、ハイマツの間に目につきます。
日の短い時期なので、帰りを急ぎます。
大分下がったところで「リンドウ」 です。 木曽五木のひとつ「ネズコ」です。


ネズコは、クロベとも言い、「この木が多いことから黒部の名がつけられた。」と聞いたことがあります。
16:30 だいぶ歩いて、ようやく登山口に到着です。

登るときには、気がつかなかった看板です。
標高1350mとあり、頂上が2670mなので、標高差 1320mです。
時間は、登りに4時間40分、下りに4時間20分 ちょうど9時間かかりました。
あす以降の、筋肉痛が気がかりなジイサンの爺ケ岳登山でした。
6:30 扇沢駅近く、籠川沿いにある登山口を出発。
7:20 急な坂を登ると、「八ッ見ベンチ」とあり、素晴らしい眺望。
カメラ片手の女性に聞くと、「正面が針ノ木岳・左手に蓮華が見える。」と教えていただく。
さらに進んで、7:40 「駅見坂」とある場所で、左に蓮華岳、右に針ノ木岳をパチリ。
下方には、扇沢の駐車場が見えます。
安曇野から見ると、針ノ木岳は蓮華岳の陰に隠れているようです。
7:50 彼方の稜線に、赤い屋根の建物が、「種池山荘」とのこと。
(クリックして大きくしてね。)
道沿いには、赤い実をつけたゴゼンタチバナ。
8:30 「一枚岩」を通過、 まもなく鮮やかな紅葉が目につくようになります。
9:30 「ガレ場」を通過。
10:00 種池山荘に到着ですが、この辺りから霧が濃くなってきます。
降りてきた人からは、「稜線は風が強く、寒い。」と、教えられる。
予備のチョッキに手袋、寒さよけの雨具を着込んで出発です。
稜線はハイマツ帯です。
霧が無ければ、周囲の山々が見えると思うのですが、黙々と進むだけです。
10:50 降りてきた人から、「少し上に、ライチョウがいますよ。」と教えていただく。
いました。3羽見えます。 家族でしょうか?
思いがけない「霧の贈り物」です。

気を良くして、歩くうちに霧も少しずつ晴れてくるようです。
11:05 爺ケ岳中峰の標識です。
11:20 山頂(2670m)です。
霧の晴れ間に撮った「針ノ木岳」と頭だけの「鹿島槍」です。
南峰(2660m)への道です。 帰り道に登ってみます。
山頂でゆっくりしていたので、12:30出発です。
来る時は、気づかなかった「シラタマノキ」です。
稜線では、チングルマ・ガンコウラン・シャクナゲなどが、ハイマツの間に目につきます。
日の短い時期なので、帰りを急ぎます。
大分下がったところで「リンドウ」 です。 木曽五木のひとつ「ネズコ」です。
ネズコは、クロベとも言い、「この木が多いことから黒部の名がつけられた。」と聞いたことがあります。
16:30 だいぶ歩いて、ようやく登山口に到着です。
登るときには、気がつかなかった看板です。
標高1350mとあり、頂上が2670mなので、標高差 1320mです。
時間は、登りに4時間40分、下りに4時間20分 ちょうど9時間かかりました。
あす以降の、筋肉痛が気がかりなジイサンの爺ケ岳登山でした。

しゅう坊の自転車特訓
幼稚園・年中さんのしゅう坊が遊びにきました。
さっそく、昨日採ってきたペチャ豆を、踏んでもらいます。 殻から豆を取り出す手伝いもします。


「補助輪を外した自転車に乗りたい。」 と言うので、
ユウ君からの、おさがりの自転車に乗ってみます。
恐るおそる乗り出しますが、 すぐに、バランスを崩して倒れます。 しゅうママも心配そうに見ています。


後ろから押さえてやれば良いと思うのですが、手を出すと嫌がるのです。
何回も転んでいるうち、いやになったのか、15分ほどでおしまいです。
夕方になって、「散歩に行きたいので、違う自転車を出して。」 と言います。
そういえば、もう1台の「おさがり自転車」があったのです。
いままで、補助輪を付けて乗っていたのですが、
この機会に補助輪を外します。
ついでに、サドルの高さを調整して、タイヤの空気も入れて。

さあ、2回目の挑戦です。
危なっかしい乗り方です。 見ていたお父さんが伴走します。


こんどは、公園で乗りたいと言います。
草が生えているので、ペダルをこぐのは大変ですが、転んでも痛くないのが良いところです。


土のところで、乗ってみます。 うまく回れないので、転んで止まります。


何回も転んで、ようやく回れるようになったので、家へ帰ります。


途中で、散歩中のお隣のワンちゃんに会いました。
乗っているところを、おじさんとワンちゃんに見てもらいます。
転ばないで、どんどん進んで、家まで帰ってきました。

おじさんからは、盛大な拍手でほめてもらいました。
シュウ坊はよほど嬉しかったのか、お風呂に入る時もはしゃいでいました。
さっそく、昨日採ってきたペチャ豆を、踏んでもらいます。 殻から豆を取り出す手伝いもします。
「補助輪を外した自転車に乗りたい。」 と言うので、
ユウ君からの、おさがりの自転車に乗ってみます。
恐るおそる乗り出しますが、 すぐに、バランスを崩して倒れます。 しゅうママも心配そうに見ています。
後ろから押さえてやれば良いと思うのですが、手を出すと嫌がるのです。
何回も転んでいるうち、いやになったのか、15分ほどでおしまいです。

夕方になって、「散歩に行きたいので、違う自転車を出して。」 と言います。
そういえば、もう1台の「おさがり自転車」があったのです。
いままで、補助輪を付けて乗っていたのですが、
この機会に補助輪を外します。
ついでに、サドルの高さを調整して、タイヤの空気も入れて。
さあ、2回目の挑戦です。
危なっかしい乗り方です。 見ていたお父さんが伴走します。
こんどは、公園で乗りたいと言います。
草が生えているので、ペダルをこぐのは大変ですが、転んでも痛くないのが良いところです。
土のところで、乗ってみます。 うまく回れないので、転んで止まります。
何回も転んで、ようやく回れるようになったので、家へ帰ります。
途中で、散歩中のお隣のワンちゃんに会いました。
乗っているところを、おじさんとワンちゃんに見てもらいます。
転ばないで、どんどん進んで、家まで帰ってきました。
おじさんからは、盛大な拍手でほめてもらいました。
シュウ坊はよほど嬉しかったのか、お風呂に入る時もはしゃいでいました。
からたきの峯に登る
「からたきの峯 市民登山」 の募集があったので参加しました。
からたきの峯(標高1857.7m)へ登るのは初めてですので、
どんな山か楽しみです。
案内していただく人も入れて、40数名ほどの人員で登山口へ向かいます。
小曽部川上流の白滝を過ぎた辺りの広場に車を止め、8:45 出発です。
ここから、送電線の巡視路を登り、林道に出たら、この看板の処を登ります。

道端には、そば打ちのつなぎに使うというオヤマボクチ・可憐な白い花をつけた
オトコエシ・黄色のアキノキリンソウ・薄紫のノコンギクなどが、足元に咲き乱れます。


9:20 新池に着きました。 ここは、二重稜線で成立した凹地だそうです。
以前は、ヒツジグサがあったが、土砂で池が埋まっていくにつれ、
ミツガシワに変わりつつあるそうです。

ここでは、雨乞いの山の神・モチの木・シャクナゲなど目につきます。
赤い実は、6月頃白い花をつけているオオカメノキです。

地元の小曽部の人たちが笹を刈りはらった登山道の脇に
ハンゴンソウの花です。

山頂に近い尾根には、少しですが天然林が残されています。
コメツガ・ブナ・ウラジロモミ・天然カラマツなどの根元に、イチヨウランです。

11:50 笹を幅広く刈ってある尾根道を辿ります。

チョウセンマツ(チョウセンゴヨウマツ)が群生しています。
れっきとした日本産ですが、単体で生育することが多く、
このように集まっていることが珍しいそうです。

12:00 頂上への最後の急坂です。

山頂には、三角点や標柱などがあり、奈良井川・九里巾などの樹木のつながりが良く分かります。
また、塩尻峠の方向には、諏訪湖が望めるのです。

八ヶ岳は雲にかくれています。(クリックして大きくしてね。)
熊にかじられたと言う標柱と三角点です。

南西の方向にも、藪を切りはらった展望場所がありますが、雲が多くて見えませんでした。
山頂でゆっくり昼食をとり、 13:15 来た時と同じ道を下り始めます。
14:00 新池です。 この付近から下は、手入れされたカラマツ林が続きます。

15:00 駐車場所へ到着です。 約6時間半の山歩きでした。
塩尻市役所の皆さん・ボランティアの皆さんお世話になりました。
貴重な経験ができ、ありがとうございました。
からたきの峯(標高1857.7m)へ登るのは初めてですので、
どんな山か楽しみです。
案内していただく人も入れて、40数名ほどの人員で登山口へ向かいます。
小曽部川上流の白滝を過ぎた辺りの広場に車を止め、8:45 出発です。
ここから、送電線の巡視路を登り、林道に出たら、この看板の処を登ります。
道端には、そば打ちのつなぎに使うというオヤマボクチ・可憐な白い花をつけた
オトコエシ・黄色のアキノキリンソウ・薄紫のノコンギクなどが、足元に咲き乱れます。
9:20 新池に着きました。 ここは、二重稜線で成立した凹地だそうです。
以前は、ヒツジグサがあったが、土砂で池が埋まっていくにつれ、
ミツガシワに変わりつつあるそうです。
ここでは、雨乞いの山の神・モチの木・シャクナゲなど目につきます。
赤い実は、6月頃白い花をつけているオオカメノキです。
地元の小曽部の人たちが笹を刈りはらった登山道の脇に
ハンゴンソウの花です。
山頂に近い尾根には、少しですが天然林が残されています。
コメツガ・ブナ・ウラジロモミ・天然カラマツなどの根元に、イチヨウランです。
11:50 笹を幅広く刈ってある尾根道を辿ります。
チョウセンマツ(チョウセンゴヨウマツ)が群生しています。
れっきとした日本産ですが、単体で生育することが多く、
このように集まっていることが珍しいそうです。
12:00 頂上への最後の急坂です。
山頂には、三角点や標柱などがあり、奈良井川・九里巾などの樹木のつながりが良く分かります。
また、塩尻峠の方向には、諏訪湖が望めるのです。
八ヶ岳は雲にかくれています。(クリックして大きくしてね。)
熊にかじられたと言う標柱と三角点です。
南西の方向にも、藪を切りはらった展望場所がありますが、雲が多くて見えませんでした。

山頂でゆっくり昼食をとり、 13:15 来た時と同じ道を下り始めます。
14:00 新池です。 この付近から下は、手入れされたカラマツ林が続きます。
15:00 駐車場所へ到着です。 約6時間半の山歩きでした。
塩尻市役所の皆さん・ボランティアの皆さんお世話になりました。
貴重な経験ができ、ありがとうございました。
9月の野菜畑
最初は、ペチャ豆の収穫です。
「ペチャ豆」とは、おかしな呼び方ですが、
花豆の仲間で、ペタンコの形から、こう呼ばれているようです。

ユウ君と一緒に畑からとってきました。
日向に広げて、乾いたら、踏んでもらいます。


妹のあやちゃんが、殻から豆を取り出す手伝いもします。

今日で、3回目の収穫です。
どのくらい採れたか、いままでの分も合わせて計ってみたら 5.2kgでした。
こんなに沢山とれたのは初めてです。
この豆は、ツルが良く伸びますので、広い棚を使ったのが良かったのでしょう。
畑に植えてあった菊のつぼみが開いてきたので、鉢にとります。

6月ごろ、新芽を畑に植えておけば自然に円い形になるので、
手がかかりません。
この色の菊は、早く咲きだします。 黄色のものは、10月になってからです。
イチゴの苗も、40株ほどとれたので、庭で10月まで大きくします。

ホンウリとカボチャの種もとります。

秋野菜も蒔きました。
8月末に蒔いたダイコンで、芽が出てきたところです。(9月4日)
ここは、キツネが出るので、踏まれないよう囲ってみました。

野沢菜なども蒔きました。
その後、雨がさっぱり降りません。
9月16日現在です。
ダイコンは、芽がきれいにそろっていますが、
その両側の野沢菜などは、芽がまばらに出ただけです。

秋の野菜は、昨年初めて作ってみました。
野沢菜・漬けダイコンなど、そこそこ採れたのですが、今年はいけません。
何日も、水を運んでやりましたが、芽が出てきません。
ようやく、昨夜、まとまった雨が降りましたので、
出なかった分の種を、追加で蒔いてみようと思っています。
「ペチャ豆」とは、おかしな呼び方ですが、
花豆の仲間で、ペタンコの形から、こう呼ばれているようです。
ユウ君と一緒に畑からとってきました。
日向に広げて、乾いたら、踏んでもらいます。
妹のあやちゃんが、殻から豆を取り出す手伝いもします。
今日で、3回目の収穫です。
どのくらい採れたか、いままでの分も合わせて計ってみたら 5.2kgでした。
こんなに沢山とれたのは初めてです。

この豆は、ツルが良く伸びますので、広い棚を使ったのが良かったのでしょう。
畑に植えてあった菊のつぼみが開いてきたので、鉢にとります。
6月ごろ、新芽を畑に植えておけば自然に円い形になるので、
手がかかりません。
この色の菊は、早く咲きだします。 黄色のものは、10月になってからです。
イチゴの苗も、40株ほどとれたので、庭で10月まで大きくします。
ホンウリとカボチャの種もとります。
秋野菜も蒔きました。
8月末に蒔いたダイコンで、芽が出てきたところです。(9月4日)
ここは、キツネが出るので、踏まれないよう囲ってみました。
野沢菜なども蒔きました。
その後、雨がさっぱり降りません。
9月16日現在です。
ダイコンは、芽がきれいにそろっていますが、
その両側の野沢菜などは、芽がまばらに出ただけです。
秋の野菜は、昨年初めて作ってみました。
野沢菜・漬けダイコンなど、そこそこ採れたのですが、今年はいけません。
何日も、水を運んでやりましたが、芽が出てきません。
ようやく、昨夜、まとまった雨が降りましたので、

出なかった分の種を、追加で蒔いてみようと思っています。
本ウリの粕漬け
暑い。 あつい。 毎日暑い日が続きます。
家内は、「まだ暑いから、漬けても酸っぱくなる。」 と、言いますが、
畑の本ウリは、「もう実ったので、漬けてほしい~。」 と、言ってます。
仕方ないので、まとめて収穫します。
ここからは、家内の出番です。
本ウリは、二つに割って 種を出し、 一晩 塩漬けします。

翌日、塩漬けしたウリを干して、水気をとります。

最後に、酒粕と砂糖で漬けこみます。
こうして、涼しいところに、1~2か月置きます。
このウリは、大町の親戚から種を分けてもらったもので、
柔らかくて、歯ごたえもあるので美味しく、楽しみです。

沢山採れたので、家内の友達 3人に10キロくらいずつ届けてあげます。

でも、一人の友達は留守です。 どうしようかと、思案していると、
隣家のお嫁さんが、「10日間ほど留守ですよ。」 と、出て見えました。
その方にお話しすると、「ぜひ漬けてみたい。」 と、タイミング良くもらっていただきました。
写真は、収穫が終わって、種取り用のウリが少し残っているだけの状態です。

今年は、6月に2回に分けて蒔いたのですが、
収穫時期は、結局一緒になってしまいました。
来年は、もっと間隔を空けて、遅めに蒔くことにしようと思います。

家内は、「まだ暑いから、漬けても酸っぱくなる。」 と、言いますが、
畑の本ウリは、「もう実ったので、漬けてほしい~。」 と、言ってます。
仕方ないので、まとめて収穫します。
ここからは、家内の出番です。
本ウリは、二つに割って 種を出し、 一晩 塩漬けします。
翌日、塩漬けしたウリを干して、水気をとります。
最後に、酒粕と砂糖で漬けこみます。
こうして、涼しいところに、1~2か月置きます。
このウリは、大町の親戚から種を分けてもらったもので、
柔らかくて、歯ごたえもあるので美味しく、楽しみです。
沢山採れたので、家内の友達 3人に10キロくらいずつ届けてあげます。
でも、一人の友達は留守です。 どうしようかと、思案していると、
隣家のお嫁さんが、「10日間ほど留守ですよ。」 と、出て見えました。
その方にお話しすると、「ぜひ漬けてみたい。」 と、タイミング良くもらっていただきました。

写真は、収穫が終わって、種取り用のウリが少し残っているだけの状態です。
今年は、6月に2回に分けて蒔いたのですが、
収穫時期は、結局一緒になってしまいました。
来年は、もっと間隔を空けて、遅めに蒔くことにしようと思います。
8月の野菜畑
ネギの頭を切りました。
近くの農家の人がするように、枯れ葉なども取り除いてみました。

きれいにした方が、病気などにかかりにくいようです。
来年用のイチゴの小苗をポットに受けてとります。
ランナーの2番目以降の苗がよいそうです。

カボチャ畑です。 花粉つけを何回かして、実がついています。

細長い種類で、美味しいそうです。

去年、友達にもらった「赤くて小さな」種類です。 普通の栗味カボチャです。


どのカボチャも、まだ収穫時期がきていません。
あまり、沢山実をつけると味が落ちるようですので、つき過ぎた若い実を取り除こうと思っています。
ペチャ豆も沢山ついています。
ツルがよく伸びるので、円形の棚に作ってみました。

すごく、茂っています。

これで、しばらくはキュウリやナスなどの収穫をしていればOKです。
近くの農家の人がするように、枯れ葉なども取り除いてみました。
きれいにした方が、病気などにかかりにくいようです。
来年用のイチゴの小苗をポットに受けてとります。
ランナーの2番目以降の苗がよいそうです。
カボチャ畑です。 花粉つけを何回かして、実がついています。
細長い種類で、美味しいそうです。
去年、友達にもらった「赤くて小さな」種類です。 普通の栗味カボチャです。
どのカボチャも、まだ収穫時期がきていません。
あまり、沢山実をつけると味が落ちるようですので、つき過ぎた若い実を取り除こうと思っています。
ペチャ豆も沢山ついています。
ツルがよく伸びるので、円形の棚に作ってみました。
すごく、茂っています。

これで、しばらくはキュウリやナスなどの収穫をしていればOKです。

ジャガイモ掘り
日曜日の朝 5時から息子とジャガイモ掘りです。
実は、しばらく前から少しずつ一人で掘っていたのですが、「量が多すぎて、
どうしようか?」と、思案していたのです。
嫁さんとしゅう坊が実家へ帰ったので、
ちょうど泊まりにきた息子に助太刀を頼んだのです。
メークインを、1列掘ったところです。

今日の予定、メークイン2列とアンデス1列を掘ったところです。

陽が高くなる前に、急いで袋に入れて集め、家の日陰に干します。
肥料の空き袋で14袋ありました。 1袋20kgとして、250kgくらいは
ありそうです。
西側の倉庫との間に広げます。
赤いのがアンデス・細長いのがメークインです。

一日干せば良いので、残りは車庫の隅に広げます。

取りあえず、暑くなる8時前に終えることができました。
あと、キタアカリが同じくらいあるので、早めに掘らなければいけません。
いつも、子供たちや親せきなどに分けてあげますが、昨年は不作だったので、
今年は、蒔きつけを増やしたのですが、「たくさん作りすぎたようです。」 続きを読む
続きを読む

実は、しばらく前から少しずつ一人で掘っていたのですが、「量が多すぎて、
どうしようか?」と、思案していたのです。
嫁さんとしゅう坊が実家へ帰ったので、
ちょうど泊まりにきた息子に助太刀を頼んだのです。
メークインを、1列掘ったところです。
今日の予定、メークイン2列とアンデス1列を掘ったところです。
陽が高くなる前に、急いで袋に入れて集め、家の日陰に干します。
肥料の空き袋で14袋ありました。 1袋20kgとして、250kgくらいは
ありそうです。
西側の倉庫との間に広げます。
赤いのがアンデス・細長いのがメークインです。
一日干せば良いので、残りは車庫の隅に広げます。
取りあえず、暑くなる8時前に終えることができました。

あと、キタアカリが同じくらいあるので、早めに掘らなければいけません。
いつも、子供たちや親せきなどに分けてあげますが、昨年は不作だったので、
今年は、蒔きつけを増やしたのですが、「たくさん作りすぎたようです。」
 続きを読む
続きを読む夏の昆虫
ユウ君の「夏休みの一研究」が、「昆虫探し」と言うので、一緒に山へ行きます。
山道で、出合った虫たちです。

アサギマダラです。

イトトンボの仲間です。 あとで調べたらオオアオイトトンボでした。
途中で出合った「地元のおじさん」から、教えてもらったクヌギの木です。

樹液の出る場所に、スズメバチ・アオカナブン・チョウなどが集まっています。
そのほかに、テントウムシ・ハナバチ・クワガタなどが見つかりました。
捕まえた虫は、写真に撮って・メモ帳に書いて、逃がしてやります。
翌日、一緒に「昆虫図鑑」やネットで名前を調べていたら、
樹液を吸っていたチョウがオオムラサキのように思えたのです。
市民プールへ行く前に、もう一度昨日の場所に行ってみました。
「いました。」 が、ユウ君は「スズメバチが怖い。」と近寄れません。
仕方ないので、私が網で捕ろうとしましたが、逃げられてしまいます。
違う木を見に行きます。 「いました。」 今度はユウ君が網をかまえます。
「入った。」 捕れたのです。

羽根を傷めないよう、そっと持ちます。

逃がす前に、もう一度、パチリ。

オオムラサキのオスです。 他に、メスも見えました。
もう一度、探しにきた甲斐がありました。
山道で、出合った虫たちです。
アサギマダラです。
イトトンボの仲間です。 あとで調べたらオオアオイトトンボでした。
途中で出合った「地元のおじさん」から、教えてもらったクヌギの木です。
樹液の出る場所に、スズメバチ・アオカナブン・チョウなどが集まっています。
そのほかに、テントウムシ・ハナバチ・クワガタなどが見つかりました。
捕まえた虫は、写真に撮って・メモ帳に書いて、逃がしてやります。
翌日、一緒に「昆虫図鑑」やネットで名前を調べていたら、
樹液を吸っていたチョウがオオムラサキのように思えたのです。
市民プールへ行く前に、もう一度昨日の場所に行ってみました。
「いました。」 が、ユウ君は「スズメバチが怖い。」と近寄れません。
仕方ないので、私が網で捕ろうとしましたが、逃げられてしまいます。

違う木を見に行きます。 「いました。」 今度はユウ君が網をかまえます。
「入った。」 捕れたのです。
羽根を傷めないよう、そっと持ちます。
逃がす前に、もう一度、パチリ。
オオムラサキのオスです。 他に、メスも見えました。
もう一度、探しにきた甲斐がありました。

グリンピースのこと
7月11日に採ったグリンピースです。

今シーズン最後ですので、 家内が、グリンピースごはんにしたり、
子供たちにあげたりして、残りを冷凍にしました。

こんなに沢山採れるとは思いませんでしたが、
「来年は、ソラマメも作って欲しい。」と、家内からの希望です。
グリンピースは、今春の3月に蒔きましたが、
ソラマメは、前年の秋に蒔かないと間に合わないようです。
「冬越しをどうするか。」 これから調べてみようと思います。
今シーズン最後ですので、 家内が、グリンピースごはんにしたり、
子供たちにあげたりして、残りを冷凍にしました。
こんなに沢山採れるとは思いませんでしたが、
「来年は、ソラマメも作って欲しい。」と、家内からの希望です。
グリンピースは、今春の3月に蒔きましたが、
ソラマメは、前年の秋に蒔かないと間に合わないようです。
「冬越しをどうするか。」 これから調べてみようと思います。
梅雨時の漬物 ②
7月18日 庭の梅が熟してきたので、残っていた梅を収穫しました。

全部で、13kgくらいありました。
もうしばらく、日陰において黄色になったら漬けこむそうです。
7月22日 梅干しなどの準備をしました。
と、言っても 家内の指示で手伝っただけですが。

① 手前のナベ二つは、梅干し用・8kgです。 1週間ほど塩水に漬けてから、
干し、塩抜きします。
② 赤いふたは、梅のサワードリンクです。 梅4kgを、酢と砂糖で漬けて、
3月程で出来上がりです。 薄めて飲むと、夏バテ防止になります。
醤油に混ぜたり、焼酎を割っても良いです。
③ 少しですが、ウメッシュも作りました。
④ 右の2本は、シソジュースです。 シソの葉に、クエン酸と砂糖で作ります。
シソの香りと、クエン酸の酸味がほど良くマッチして、
冷水で割って飲むとおいしいです。
最初、青いうちに取った梅は、甘めのカリカリウメ 3kgになりましたので、
全部で 16kg収穫できたことになります。
これでも、子供たち等にあげれば、ほぼ終わります。
家内 「あ~あ 疲れた。」 「取りあえず、晴天が続きますように。」
全部で、13kgくらいありました。
もうしばらく、日陰において黄色になったら漬けこむそうです。
7月22日 梅干しなどの準備をしました。
と、言っても 家内の指示で手伝っただけですが。
① 手前のナベ二つは、梅干し用・8kgです。 1週間ほど塩水に漬けてから、
干し、塩抜きします。
② 赤いふたは、梅のサワードリンクです。 梅4kgを、酢と砂糖で漬けて、
3月程で出来上がりです。 薄めて飲むと、夏バテ防止になります。
醤油に混ぜたり、焼酎を割っても良いです。
③ 少しですが、ウメッシュも作りました。
④ 右の2本は、シソジュースです。 シソの葉に、クエン酸と砂糖で作ります。
シソの香りと、クエン酸の酸味がほど良くマッチして、
冷水で割って飲むとおいしいです。
最初、青いうちに取った梅は、甘めのカリカリウメ 3kgになりましたので、
全部で 16kg収穫できたことになります。
これでも、子供たち等にあげれば、ほぼ終わります。
家内 「あ~あ 疲れた。」 「取りあえず、晴天が続きますように。」

クワガタムシ
海の日に、娘家族から夕食に誘われた。
夕飯前に、「カブトムシを探しに行く。」と言うので、一緒に行くことにした。
ユウ君とお父さんは、去年 この川の河川敷で、クワガタを捕ったいう。
ススキや雑草の生い茂る草原を、ヤナギ・アカシヤなどの木を見つけて探す。
まだ陽が高いので、「暑い」・尺取虫や毛虫が背中や肩にくっつく。
なかなか見つからない。
あまりに大変なので、草を刈ってある土手に上がって、手近の樹木を探すことになった。
いました。 クワガタのメスです。 写真 右上にオスも見えます。
写真 右上にオスも見えます。

ユウ君が、下から透かして見ています。 虫取り網を伸ばしています。 見つけたようです。


捕まえました。 オスのノコギリクワガタです。

今度は、お父さんと一緒です。


地面に落ちてしまったのですが、見つかりました。
こうして、何箇所かで7匹ほど捕れました。

しばらく飼育して、
お盆にはこの場所に帰してやる約束で
家へ持ち帰ります。
クワガタが沢山捕れて、ユウ君は大喜びでしたが、こちらも童心にかえって
大いに楽しみました。
そのあと わたしは、首筋や背中が痒くてたまらないので、
シャワーを借りてようやく人心地でした。
夕飯前に、「カブトムシを探しに行く。」と言うので、一緒に行くことにした。
ユウ君とお父さんは、去年 この川の河川敷で、クワガタを捕ったいう。
ススキや雑草の生い茂る草原を、ヤナギ・アカシヤなどの木を見つけて探す。
まだ陽が高いので、「暑い」・尺取虫や毛虫が背中や肩にくっつく。

なかなか見つからない。
あまりに大変なので、草を刈ってある土手に上がって、手近の樹木を探すことになった。
いました。 クワガタのメスです。
 写真 右上にオスも見えます。
写真 右上にオスも見えます。ユウ君が、下から透かして見ています。 虫取り網を伸ばしています。 見つけたようです。
捕まえました。 オスのノコギリクワガタです。
今度は、お父さんと一緒です。
地面に落ちてしまったのですが、見つかりました。
こうして、何箇所かで7匹ほど捕れました。
しばらく飼育して、
お盆にはこの場所に帰してやる約束で
家へ持ち帰ります。
クワガタが沢山捕れて、ユウ君は大喜びでしたが、こちらも童心にかえって
大いに楽しみました。

そのあと わたしは、首筋や背中が痒くてたまらないので、
シャワーを借りてようやく人心地でした。
梅雨時の漬物
久しぶりに、我が家の梅の木に、沢山実がつきました。

息子が小学校入学の時、長野市からいただいた記念の樹で、
5年生の時、長野から一緒に引っ越してきた豊後(ブンゴ)と言う種類です。
家内は、先日、南高梅で梅干しを作り、
さらに、竜峡小梅とこの豊後でカリカリ梅漬けを漬けましたが、
まだまだ、実が沢山ついているので、熟すまで木において、
さらに、さらに、梅干しと梅酢も作ろうと意気込んでいます。
(梅干しばあさんの本領発揮です。 )
)
栽培を始めてから、2年目のラッキョウも沢山とれました。
梅雨の晴れ間を見て、掘り取ったラッキョウをきれいに作って計ってみました。

約4kgありました。
とりあえず、塩漬けにして2週間おいておくそうです。
息子が小学校入学の時、長野市からいただいた記念の樹で、
5年生の時、長野から一緒に引っ越してきた豊後(ブンゴ)と言う種類です。
家内は、先日、南高梅で梅干しを作り、
さらに、竜峡小梅とこの豊後でカリカリ梅漬けを漬けましたが、
まだまだ、実が沢山ついているので、熟すまで木において、
さらに、さらに、梅干しと梅酢も作ろうと意気込んでいます。
(梅干しばあさんの本領発揮です。
 )
)栽培を始めてから、2年目のラッキョウも沢山とれました。
梅雨の晴れ間を見て、掘り取ったラッキョウをきれいに作って計ってみました。
約4kgありました。
とりあえず、塩漬けにして2週間おいておくそうです。
しゅう坊の釣りデビュー
「日曜日に、しゅう坊と釣りに行きたい。」と、息子から電話があった。
雨模様の天気だったのでどうしようか迷っていたが、
待ち合わせ場所に行ってみると、
しゅう坊は、カッパに長靴の完全装備で、「とても楽しみにしていた。」とのこと。
かくして、幼稚園生のしゅう坊の釣りデビューとなりました。

折よく、あまり雨の当たらない場所があったので、ここで釣ってみます。
竿は、「神戸のおじいちゃんからもらった、3,5mのヤマメ竿」です。

最初は難しいので、息子が仕掛けを流します。
そして、魚が食いついたら、しゅう坊に竿を渡すようにしたのです。
さっそく、ウグイが釣れました。

産卵時期で、お腹に赤いスジが入っています。 エサはクロカワムシです。
こうして、アブラハヤなども何匹か釣ってから、一人で釣らせてみます。
おっと、釣れました。元気に跳ねています。 小さいけれど ニジマスです。


ニジマスは、漁協で放流したものでしょうから、すぐに放してやります。
川岸の草むらを網でジャブジャブします。 アブラハヤとドジョウです。


あまり簡単にいろいろな魚が捕れるので、一緒に来たしゅうママが驚いていました。
最後に、キープしてあったウグイなどを流れに戻してやって、
シュウ坊の釣りデビューは、無事に終えました。

元の場所に、元気で帰って行きます。
雨模様の天気だったのでどうしようか迷っていたが、
待ち合わせ場所に行ってみると、
しゅう坊は、カッパに長靴の完全装備で、「とても楽しみにしていた。」とのこと。
かくして、幼稚園生のしゅう坊の釣りデビューとなりました。
折よく、あまり雨の当たらない場所があったので、ここで釣ってみます。
竿は、「神戸のおじいちゃんからもらった、3,5mのヤマメ竿」です。

最初は難しいので、息子が仕掛けを流します。
そして、魚が食いついたら、しゅう坊に竿を渡すようにしたのです。
さっそく、ウグイが釣れました。
産卵時期で、お腹に赤いスジが入っています。 エサはクロカワムシです。
こうして、アブラハヤなども何匹か釣ってから、一人で釣らせてみます。
おっと、釣れました。元気に跳ねています。 小さいけれど ニジマスです。
ニジマスは、漁協で放流したものでしょうから、すぐに放してやります。
川岸の草むらを網でジャブジャブします。 アブラハヤとドジョウです。
あまり簡単にいろいろな魚が捕れるので、一緒に来たしゅうママが驚いていました。

最後に、キープしてあったウグイなどを流れに戻してやって、
シュウ坊の釣りデビューは、無事に終えました。
元の場所に、元気で帰って行きます。
6月の野菜畑
6月20日 台風4号の通過した朝 畑に行ってみました。
風は強いですが、朝から気温が高く、蒸し暑い日です。
最初に、いま収穫中のエンドウなどの畑です。

一昨日、ユウ君に一緒に採ってもらったエンドウです。
今日も、また採らないと、実が大きくなりすぎます。
次は、スナップエンドウです。 実がだいぶ大きくなっているので、
初めて、今日収穫します。

これは、グリーンピースです。 まだサヤの中の実が小さいので、
今日は収穫しません。

イチゴは、もうほとんどお終いです。
5月27日に、シュウ坊が初めて採りましたから、一か月近く楽しんだことになります。 右の写真は、ニンニク・奥がラッキョウで、まもなく収穫です。


右の少し高い畝が、サツマイモ・左のマルチシートがカボチャです。
どちらも、まだ小さいですが順調に育っています。

エンドウ(右側)とスナップエンドウです。
エンドウは1.4kgもあり、色々な人にあげました。

もう一か所の畑も見ます。
一度、土寄せをしたジャガイモは、ようやく大きくなってきました。

シシトウ・ナス・ミニトマトなどの黒いマルチは、虫よけネットを外しました。
でも、良く見るとアブラムシがついています。 きっと植えた苗についてた
のでしょう。 手で取るか、消毒することになります。
右側の白いビニールは、トマト(桃太郎)です。
支柱を1.8mの長さにする予定です。

逆方向から、撮ったものですが、ネットにはモロッコとキュウリの種を蒔いて
あり、ようやく伸びてきました。

ズッキーニの苗を4本もらいました。
花が咲いたら、その朝に受粉してやらないと良い実がつかないそうです。
奥の支柱を組んだところには、白い豆(名前はわかりません)を蒔きました。
片丘地区で、古くから作っている豆だそうです。
去年種をいただき、美味しかったので今年も作ります。 右の写真は、鞍掛豆・トウモロコシ・マルチが里芋です。


そのほかに、ホンウリ・ネギ・ペチャ豆・枝豆などもあり、この調子では
毎日2~3時間くらいは畑に行くことになります。
野菜づくりが面白くて、つい色々と作りすぎてしまいますが、
暑い夏は、頑張りすぎないよう適当に手抜きしてやっていこうと思っています
風は強いですが、朝から気温が高く、蒸し暑い日です。
最初に、いま収穫中のエンドウなどの畑です。
一昨日、ユウ君に一緒に採ってもらったエンドウです。
今日も、また採らないと、実が大きくなりすぎます。
次は、スナップエンドウです。 実がだいぶ大きくなっているので、
初めて、今日収穫します。
これは、グリーンピースです。 まだサヤの中の実が小さいので、
今日は収穫しません。
イチゴは、もうほとんどお終いです。
5月27日に、シュウ坊が初めて採りましたから、一か月近く楽しんだことになります。 右の写真は、ニンニク・奥がラッキョウで、まもなく収穫です。
右の少し高い畝が、サツマイモ・左のマルチシートがカボチャです。
どちらも、まだ小さいですが順調に育っています。
エンドウ(右側)とスナップエンドウです。
エンドウは1.4kgもあり、色々な人にあげました。
もう一か所の畑も見ます。
一度、土寄せをしたジャガイモは、ようやく大きくなってきました。
シシトウ・ナス・ミニトマトなどの黒いマルチは、虫よけネットを外しました。
でも、良く見るとアブラムシがついています。 きっと植えた苗についてた
のでしょう。 手で取るか、消毒することになります。
右側の白いビニールは、トマト(桃太郎)です。
支柱を1.8mの長さにする予定です。
逆方向から、撮ったものですが、ネットにはモロッコとキュウリの種を蒔いて
あり、ようやく伸びてきました。
ズッキーニの苗を4本もらいました。
花が咲いたら、その朝に受粉してやらないと良い実がつかないそうです。
奥の支柱を組んだところには、白い豆(名前はわかりません)を蒔きました。
片丘地区で、古くから作っている豆だそうです。
去年種をいただき、美味しかったので今年も作ります。 右の写真は、鞍掛豆・トウモロコシ・マルチが里芋です。
そのほかに、ホンウリ・ネギ・ペチャ豆・枝豆などもあり、この調子では
毎日2~3時間くらいは畑に行くことになります。
野菜づくりが面白くて、つい色々と作りすぎてしまいますが、
暑い夏は、頑張りすぎないよう適当に手抜きしてやっていこうと思っています

初夏の渓流
友達から誘ってもらい、渓流釣りに出かけました。
私は初めての川なので、どんなところか楽しみです。
久しぶりの、気の合う仲間3人での釣行です。
車を止めてから、林道を30分ほど歩きます。
お互いに近況を話しながら、鮮やかな新緑の道を釣り場へ辿ります。
最初に、支流に入ってみます。

苔むす岩の間を縫うように勢いよく水が流れ落ちます。
試しに、手を流れに浸してみると、痺れるほど冷たいのです。
まもなく当たりです。 竿を立てているFさんに小ぶりのイワナです。
時期が良くてイワナの活性が高いので、小さくても引きが強く、
竿先を絞り込むのです。
「放流サイズ。」と、言っていると、 すぐ上流のDさんにも釣れました。

手前のイワナはまずまずの大きさ、キープです。

(クリックして大きくしてね。)
Fさんが、「ニッコウイワナ」と言います。
たしかに、いつも行く木曽川水系のイワナとは斑点の色が少し違うようです。
小さな渓流なので、3人でトップを交代しながら釣り上ります。
川岸には、イワカガミの花や黄色い花をつけるタマガワホトトギス・
カタバミの白い花などが目につきます。

良い感じの流れです。
楽しみながら、ゆっくり釣りあがります。

(クリックして大きくしてね。)
途中で、1/3くらいの水量で支流が流入している箇所があり、
この奥へは、Fさんも「行ったことがない。」と言います。
時間も、大分経っているので昼食を食べてから、「あと30分だけ。」
遡ってみます。

ここまで、いくつかの滝を超えて釣りあがってきました。
魚はいますが、サイズも小さくなってきたので、この地点までとします。
釣り始めてから、4時間半です。
川沿いの樵道を下って、林道の手前でコーヒーを沸かして一休み。
約1時間半で駐車場所に到着です。
帰り道も、立派な「カツラの大木」や「トチの木の白い花」、「おとし文」など興味はつきません。
(カツラは、古い時代に香木として匂いを楽しんだという。)、(パリのマロニエは、トチの仲間。)、(オトシブミを開いて、卵を見たり。)
こうして、仲間との楽しかった渓流釣りの一日は終わり、
それぞれ、数匹のイワナを、奥方へのお土産に帰路につきました。
私は初めての川なので、どんなところか楽しみです。
久しぶりの、気の合う仲間3人での釣行です。
車を止めてから、林道を30分ほど歩きます。
お互いに近況を話しながら、鮮やかな新緑の道を釣り場へ辿ります。
最初に、支流に入ってみます。

苔むす岩の間を縫うように勢いよく水が流れ落ちます。
試しに、手を流れに浸してみると、痺れるほど冷たいのです。
まもなく当たりです。 竿を立てているFさんに小ぶりのイワナです。
時期が良くてイワナの活性が高いので、小さくても引きが強く、
竿先を絞り込むのです。
「放流サイズ。」と、言っていると、 すぐ上流のDさんにも釣れました。

手前のイワナはまずまずの大きさ、キープです。

(クリックして大きくしてね。)
Fさんが、「ニッコウイワナ」と言います。
たしかに、いつも行く木曽川水系のイワナとは斑点の色が少し違うようです。
小さな渓流なので、3人でトップを交代しながら釣り上ります。
川岸には、イワカガミの花や黄色い花をつけるタマガワホトトギス・
カタバミの白い花などが目につきます。

良い感じの流れです。
楽しみながら、ゆっくり釣りあがります。

(クリックして大きくしてね。)
途中で、1/3くらいの水量で支流が流入している箇所があり、
この奥へは、Fさんも「行ったことがない。」と言います。
時間も、大分経っているので昼食を食べてから、「あと30分だけ。」
遡ってみます。

ここまで、いくつかの滝を超えて釣りあがってきました。
魚はいますが、サイズも小さくなってきたので、この地点までとします。
釣り始めてから、4時間半です。
川沿いの樵道を下って、林道の手前でコーヒーを沸かして一休み。
約1時間半で駐車場所に到着です。
帰り道も、立派な「カツラの大木」や「トチの木の白い花」、「おとし文」など興味はつきません。
(カツラは、古い時代に香木として匂いを楽しんだという。)、(パリのマロニエは、トチの仲間。)、(オトシブミを開いて、卵を見たり。)
こうして、仲間との楽しかった渓流釣りの一日は終わり、
それぞれ、数匹のイワナを、奥方へのお土産に帰路につきました。