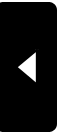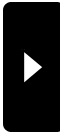夏野菜の畑
夏野菜の植え付け・種まきなどが一段落しました。
ジャガイモは、5月13日の強い霜で葉が傷んだので、
株の大きさにバラツキがあります。
早めに、追肥・土寄せをしたほうが良さそうです。

手前の長い畝は、ナス・ピーマン・シシトウ・ミニトマトです。
ジャガイモと同じナス科のため、分かりやすくまとめて、来年の連作を避ける
ようにしました。
背の高いビニールは、トマトの桃太郎です。
それぞれ、虫よけネットで強い風や虫を避けるようにしてみました。

もう一つのネットは、キュウリとモロッコインゲンです。
種を直播きしました。 芽の出ないところもあるので、追加して蒔きます。

手前のトウモロコシ・枝豆は、芽が出そろっています。
奥の白いネットは鞍掛豆ですが、
芽が出始めた時、鳥に食べられたので急いでネットを掛け、種を追加蒔きしました。

反対側から写しました。
右から、鞍掛豆・里芋・秋に円くなる菊が10本です。

ここまでが今年から借りた畑で、他にも蒔いてありますが、
まだまだ、土がむき出しのところが多い感じです。
次が、いままで作っていた畑です。
手前の高い畝が、サツマイモ(ベニアズマ)で、黒いマルチがカボチャです。
クリアジ・伯爵・細長いもの・3種類カボチャの種を蒔いてみました。

3月に種を蒔いたエンドウです。 白い花が咲いています。
右の写真は、スナップエンドウでグリンピースもありますが、
エンドウが一番早いようで、似た者3兄弟です。
また、松本一本ネギも見えます。


これは、シオデです。「木曽駒道の駅」で小さな苗を買ってきて、5年ほどになり、ようやく採れる大きさに育ちました。
右の写真もそうですが、野生のアスパラガスとも言われます。


今日は、しゅう坊が来たのでイチゴとりです。


ちょうど良い時期です。 「おいしい 味も濃い。」と好評でした。
日々、色づいていくので、しばらくは「ユウ君たち」も一緒に楽しめることでしょう。
ジャガイモは、5月13日の強い霜で葉が傷んだので、
株の大きさにバラツキがあります。
早めに、追肥・土寄せをしたほうが良さそうです。
手前の長い畝は、ナス・ピーマン・シシトウ・ミニトマトです。
ジャガイモと同じナス科のため、分かりやすくまとめて、来年の連作を避ける
ようにしました。
背の高いビニールは、トマトの桃太郎です。
それぞれ、虫よけネットで強い風や虫を避けるようにしてみました。
もう一つのネットは、キュウリとモロッコインゲンです。
種を直播きしました。 芽の出ないところもあるので、追加して蒔きます。
手前のトウモロコシ・枝豆は、芽が出そろっています。
奥の白いネットは鞍掛豆ですが、
芽が出始めた時、鳥に食べられたので急いでネットを掛け、種を追加蒔きしました。
反対側から写しました。
右から、鞍掛豆・里芋・秋に円くなる菊が10本です。
ここまでが今年から借りた畑で、他にも蒔いてありますが、
まだまだ、土がむき出しのところが多い感じです。
次が、いままで作っていた畑です。
手前の高い畝が、サツマイモ(ベニアズマ)で、黒いマルチがカボチャです。
クリアジ・伯爵・細長いもの・3種類カボチャの種を蒔いてみました。
3月に種を蒔いたエンドウです。 白い花が咲いています。
右の写真は、スナップエンドウでグリンピースもありますが、
エンドウが一番早いようで、似た者3兄弟です。
また、松本一本ネギも見えます。
これは、シオデです。「木曽駒道の駅」で小さな苗を買ってきて、5年ほどになり、ようやく採れる大きさに育ちました。
右の写真もそうですが、野生のアスパラガスとも言われます。
今日は、しゅう坊が来たのでイチゴとりです。
ちょうど良い時期です。 「おいしい 味も濃い。」と好評でした。
日々、色づいていくので、しばらくは「ユウ君たち」も一緒に楽しめることでしょう。

魚釣りと生き物探し ②
娘から「用事があるので、ユウ君を預かって。」と、頼まれたので、
近くの川に、釣り道具とタモ網を持って遊びに行った。
釣りエサの川虫を捕ろうと、網を当てて石を裏返したら、
サワガニの子供が入ってきた。(ホントに小さいのでクリックしてね。)

エサを捕って、さっそく釣り始めます。

田圃に水を取りだしたので、水量が減っています。
今日は、あまり釣れないかな~。と思っているとーーーーーー。
来ました。

ヤマメです。 20センチくらいか。
この場所は、この1匹だけでしたが、少しずつ場所を移して、
アグラハヤ、ウグイ、ヤマメを釣っては、逃がしていきます。
「子供専用釣り場」の看板のところで、やってみます。

ここで、ヤマメが1匹釣れたので、網で水の中の草むらをガサガサします。

珍しいトノサマガエルです。 久しぶりに見ました。
お昼時間になったので、最後の場所です。 大きな当たりと引きです。


ヤマメの大物です。 「この魚だけは持ち帰りしたい。」と言うので、
家で調理してもらうことにします。
家で計ってみると、長さ30センチに1センチ足りないサイズでした。
娘は、「から揚げ」にするそうです。
楽しかった川遊びでしたが、失敗はユウ君が何かの虫に刺されたらしく、
後で薬を付けたり大変でした。 (暑かったので、半そでシャツだったのです。)
近くの川に、釣り道具とタモ網を持って遊びに行った。
釣りエサの川虫を捕ろうと、網を当てて石を裏返したら、
サワガニの子供が入ってきた。(ホントに小さいのでクリックしてね。)

エサを捕って、さっそく釣り始めます。

田圃に水を取りだしたので、水量が減っています。
今日は、あまり釣れないかな~。と思っているとーーーーーー。
来ました。

ヤマメです。 20センチくらいか。
この場所は、この1匹だけでしたが、少しずつ場所を移して、
アグラハヤ、ウグイ、ヤマメを釣っては、逃がしていきます。
「子供専用釣り場」の看板のところで、やってみます。

ここで、ヤマメが1匹釣れたので、網で水の中の草むらをガサガサします。

珍しいトノサマガエルです。 久しぶりに見ました。
お昼時間になったので、最後の場所です。 大きな当たりと引きです。


ヤマメの大物です。 「この魚だけは持ち帰りしたい。」と言うので、
家で調理してもらうことにします。
家で計ってみると、長さ30センチに1センチ足りないサイズでした。
娘は、「から揚げ」にするそうです。
楽しかった川遊びでしたが、失敗はユウ君が何かの虫に刺されたらしく、
後で薬を付けたり大変でした。 (暑かったので、半そでシャツだったのです。)
ぐるりと回って、烏帽子岩へ
最初は、カヤの平へ「ブナの新緑」を見に行く予定でしたが、
「まだ雪がたくさん残っている。」と言うことで、松本市三才山の烏帽子岩に
変更です。
8;40 三才山トンネルの入り口・北側(左)から入山します。
2万5千分の1の地図で、標高が、1100mくらいです。

送電線の巡視路を利用させてもらうのですが、
沢に沿った崩れやすい道のため、慎重に進みます。
道沿いには、モミジガサ・ヤブレガサや毒草のハシリドコロがあります。

カラマツは、芽吹いたばかりに見えます。

10:00 小雨のなか、稜線に立つ鉄塔に着きました。
西の方向に、以前歩いたことのある戸谷峰(1629m)が見えます。

何となく気品ありげなルイヨウボタンです。後方の大きな葉っぱは、
コバイケイソウです。

11:20 六人坊(1618m)に到着です。
ここには三角点があり、「美ヶ原トレイル」として整備が進んでいるそうです。
ヤマザクラが咲きだして、ミツバツツジ・ドウダンはつぼみですが、
開花寸前という状態です。

12:00 三才山峠(1605m)に着きました。 昼食をとります。
この峠は、古代から交通の要所として利用されていたようです。
いつも思うのですが、「昔の人は、本当に足が強かった。」のですね。

ここからは、林道蝶ケ原線を歩きます。
遠くに目的地の「烏帽子岩」が見えます。
ここに写っているのは、カエデの花です。

このカエデの種類は分かりませんが、枝が張って立派な樹形をした大木です。
ほかに、ウリハダカエデの花も咲いていました。
林道からすぐのところに、烏帽子岩が見える位置まで来ました。

13:15 烏帽子岩(1621m)到着です。
落ちないよう、交代にザイルで確保してもらって写しました。
南には、美ヶ原の武石峰(1972m)が望め、西には松本平から島々谷が
見えます。
天気が良ければ、北アルプスが望むことができるのです。

また、松本市島内から来た仲間の一人は、
烏帽子岩が自宅から見えるそうです。
こうして、周囲の景色を楽しんだ後、一之瀬まで下ります。
約1時間歩いて、15:30 到着です。
今日のコースは、三才山を中心にぐるりと
円を描いたことになり、
休憩時間を含むと、約8時間・歩行数で
20、000歩余りでした。
今回は、時期が良く、数々の花に巡り合えたのも幸いだったと思います。
ニリンソウ、エンゴサク、アマナ、3種類のスミレ、ヒメイチゲ、タケシマラン、
ツバメオモト、エンレイソウ、ウスバサイシン、ヒトリシズカ、カタバミなどです。
「まだ雪がたくさん残っている。」と言うことで、松本市三才山の烏帽子岩に
変更です。
8;40 三才山トンネルの入り口・北側(左)から入山します。
2万5千分の1の地図で、標高が、1100mくらいです。
送電線の巡視路を利用させてもらうのですが、
沢に沿った崩れやすい道のため、慎重に進みます。
道沿いには、モミジガサ・ヤブレガサや毒草のハシリドコロがあります。
カラマツは、芽吹いたばかりに見えます。
10:00 小雨のなか、稜線に立つ鉄塔に着きました。
西の方向に、以前歩いたことのある戸谷峰(1629m)が見えます。
何となく気品ありげなルイヨウボタンです。後方の大きな葉っぱは、
コバイケイソウです。
11:20 六人坊(1618m)に到着です。
ここには三角点があり、「美ヶ原トレイル」として整備が進んでいるそうです。
ヤマザクラが咲きだして、ミツバツツジ・ドウダンはつぼみですが、
開花寸前という状態です。
12:00 三才山峠(1605m)に着きました。 昼食をとります。
この峠は、古代から交通の要所として利用されていたようです。
いつも思うのですが、「昔の人は、本当に足が強かった。」のですね。
ここからは、林道蝶ケ原線を歩きます。
遠くに目的地の「烏帽子岩」が見えます。
ここに写っているのは、カエデの花です。
このカエデの種類は分かりませんが、枝が張って立派な樹形をした大木です。
ほかに、ウリハダカエデの花も咲いていました。
林道からすぐのところに、烏帽子岩が見える位置まで来ました。
13:15 烏帽子岩(1621m)到着です。
落ちないよう、交代にザイルで確保してもらって写しました。
南には、美ヶ原の武石峰(1972m)が望め、西には松本平から島々谷が
見えます。
天気が良ければ、北アルプスが望むことができるのです。
また、松本市島内から来た仲間の一人は、
烏帽子岩が自宅から見えるそうです。
こうして、周囲の景色を楽しんだ後、一之瀬まで下ります。
約1時間歩いて、15:30 到着です。
今日のコースは、三才山を中心にぐるりと
円を描いたことになり、
休憩時間を含むと、約8時間・歩行数で
20、000歩余りでした。
今回は、時期が良く、数々の花に巡り合えたのも幸いだったと思います。
ニリンソウ、エンゴサク、アマナ、3種類のスミレ、ヒメイチゲ、タケシマラン、
ツバメオモト、エンレイソウ、ウスバサイシン、ヒトリシズカ、カタバミなどです。
春の里山
連休明けに、山の仲間と塩尻市近郊の山を歩いてみました。
歩きだして、すぐです。 「 カモシカ。」 の声に右手を見るとーーー。
遠ざかるように歩いていましたが、こちらに興味を持ったのか、立ち止まって
見ています。 (クリックして大きくしてね。)

カラマツ林を最近間伐したようで、倒木がゴロゴロしています。
生き物では、他にサルの群れ・ヤマカガシ(蛇)に出合いました。
イカリソウです。
雪の多い県北のものは、白色が多いようです。

シジュウカラの声に励まされながら、尾根道を歩きます。
麓から尾根まで間伐してあるので、林内は見通しが良いです。
山の中がきれいになると、山野草などは増えるように思います。

ササユリです。もう少し大きな株になると、ピンクの花をつけるでしょう。
下はチゴユリです。


そのほかに、ここにはスミレ、ヒトリシズカなどが咲いていました。
山菜採りも目的でしたが、今年は思いのほか「季節が早く進んで」、コシアブラ・タラノメなどの時期が過ぎていました。
この花は、数日後、違う場所で見つけました。
白い花弁の先が少しピンクがかっています。
サラサドウダンとも違うようで、初めて見ました。

ほかに、ミツバツツジ・ハルリンドウ・スミレの仲間など。
そういえば、黒々としたクマの落し物も、早くもありました。
歩きだして、すぐです。 「 カモシカ。」 の声に右手を見るとーーー。
遠ざかるように歩いていましたが、こちらに興味を持ったのか、立ち止まって
見ています。 (クリックして大きくしてね。)
カラマツ林を最近間伐したようで、倒木がゴロゴロしています。
生き物では、他にサルの群れ・ヤマカガシ(蛇)に出合いました。
イカリソウです。
雪の多い県北のものは、白色が多いようです。
シジュウカラの声に励まされながら、尾根道を歩きます。
麓から尾根まで間伐してあるので、林内は見通しが良いです。
山の中がきれいになると、山野草などは増えるように思います。
ササユリです。もう少し大きな株になると、ピンクの花をつけるでしょう。
下はチゴユリです。
そのほかに、ここにはスミレ、ヒトリシズカなどが咲いていました。
山菜採りも目的でしたが、今年は思いのほか「季節が早く進んで」、コシアブラ・タラノメなどの時期が過ぎていました。
この花は、数日後、違う場所で見つけました。
白い花弁の先が少しピンクがかっています。
サラサドウダンとも違うようで、初めて見ました。
ほかに、ミツバツツジ・ハルリンドウ・スミレの仲間など。
そういえば、黒々としたクマの落し物も、早くもありました。

魚釣りと生き物探し
ユウ君と、いつもの川に行ってみました。
よその場所ですが、春休みに一度行ったとき、
まったく釣れなかったので今回はリベンジです。
最初にエサの川虫を採ります。 捕っていると思ったら、サワガニです。


でも、流れの石を裏返すと沢山います。

今日は、脈釣りです。仕掛けをゆっくり流すと、釣れました。 ウグイです。


産卵時期を迎えて、お腹が赤く色づいています。 またまた、ウグイです。


上流へ移動します。 ユウ君も5年生になったので、
エサ付けや針から魚を外すことを自分でやらせてみます。
そうして、何回か仕掛けを流していると、竿先がしなってグングン引き込まれます。

ヤマメです。 20センチくらいありそうです。 すぐリリースします。
今日は、魚は持ち帰りません。
同じ堰堤の下で、何回か粘っていると またまた大きな当たりです。
柔らかい竿なので、上げるのに苦労していましたが、最後はタモですくってやりました。

さっきのより、大きなヤマメです。
近くで見ていた、釣りのおじいさんが「欲しい。」と言うので、この魚はあげました。
この写真を撮ったとき、カメラを川に落としてしまったので、後の写真はありません。
このあと、場所を移動している時、 ユウ君が「あ、何かいる。」と言います。
見ると、対岸のススキの中を「黄色の小動物」が走っていきます。
やや細長く、すばしっこい動きです。 テンです。 驚きました。
釣りをしているとき、もう一度姿を見せてくれました。 こういう処に居るのですね。
そのあと、オスのキジも見ることができたのです。
今日は、どういう日でしょう。
もう一度、場所を変えてから、釣りに飽きたユウ君と、タモで流れの草むらをガサガサしました。
ドジョウ、川エビ、ヤゴ、コオイムシなど捕れたので、
1か月だけ飼ったら、川へ帰してやる約束で、「ドジョウ4匹と川エビ3匹」を家へ持ち帰りました。
(夏になって、水が温まると死んでしまうのです。)
夏のような日差しを浴びて、3時間ほどの川遊びでしたが、楽しいひとときでした。
続きを読む
よその場所ですが、春休みに一度行ったとき、
まったく釣れなかったので今回はリベンジです。
最初にエサの川虫を採ります。 捕っていると思ったら、サワガニです。
でも、流れの石を裏返すと沢山います。
今日は、脈釣りです。仕掛けをゆっくり流すと、釣れました。 ウグイです。
産卵時期を迎えて、お腹が赤く色づいています。 またまた、ウグイです。
上流へ移動します。 ユウ君も5年生になったので、
エサ付けや針から魚を外すことを自分でやらせてみます。
そうして、何回か仕掛けを流していると、竿先がしなってグングン引き込まれます。
ヤマメです。 20センチくらいありそうです。 すぐリリースします。
今日は、魚は持ち帰りません。
同じ堰堤の下で、何回か粘っていると またまた大きな当たりです。
柔らかい竿なので、上げるのに苦労していましたが、最後はタモですくってやりました。
さっきのより、大きなヤマメです。
近くで見ていた、釣りのおじいさんが「欲しい。」と言うので、この魚はあげました。
この写真を撮ったとき、カメラを川に落としてしまったので、後の写真はありません。

このあと、場所を移動している時、 ユウ君が「あ、何かいる。」と言います。
見ると、対岸のススキの中を「黄色の小動物」が走っていきます。
やや細長く、すばしっこい動きです。 テンです。 驚きました。
釣りをしているとき、もう一度姿を見せてくれました。 こういう処に居るのですね。
そのあと、オスのキジも見ることができたのです。
今日は、どういう日でしょう。

もう一度、場所を変えてから、釣りに飽きたユウ君と、タモで流れの草むらをガサガサしました。
ドジョウ、川エビ、ヤゴ、コオイムシなど捕れたので、
1か月だけ飼ったら、川へ帰してやる約束で、「ドジョウ4匹と川エビ3匹」を家へ持ち帰りました。
(夏になって、水が温まると死んでしまうのです。)
夏のような日差しを浴びて、3時間ほどの川遊びでしたが、楽しいひとときでした。
続きを読む
子檀嶺岳を歩く
子檀嶺岳(コマユミダケ)、読むことが難しい山ですが、いつもの仲間と登って
きました。

青木村の道の駅から見たところです。
ちょっと変わった恰好をしていますが、山頂まで1時間30分ほどの歩きやすい山でした。
松本駅――田沢―― 西条―― R143号― 青木峠


よく見かける蝶のさなぎ、 裸木や枯れ草の山では、目につきます。
何という蝶でしょうか。

ダンコウバイ 尾根や山頂で見かけました。
葉芽の展開に先駆けて、黄色い花を咲かせます。
茎を折り取ると、ツンとした香りが漂います。

登り口に、12:30到着です。
もう一山と、行きたいところですが、雨が降りそうなので
近くの大法寺を参拝します。
 国宝の三重塔です。
国宝の三重塔です。
見返りの塔とも言われ
古くから親しまれているそうです。
シダレザクラが咲きはじめて
います。
境内には、赤いよだれかけの
六地蔵様、ユーモラスな
羅漢の石像、カヤの巨木、
足元の小さな草花など
心が和む風景に満ちています。
境内の梅林の向こうに、夫神山(オガミヤマ)が見えました。
今日登った子檀嶺岳(コマユミダケ)と、十観山(ジュッカンヤマ)で
青木村三山と言うそうです。 また、来たいと思います。

帰りは、田沢温泉の有乳湯(ウチユ)を楽しみます。
石畳の坂道に沿った、落ち着いた感じの温泉街です。
ぬるめのお湯に浸かって、ゆったりとくつろいで帰ります。
きました。
青木村の道の駅から見たところです。
ちょっと変わった恰好をしていますが、山頂まで1時間30分ほどの歩きやすい山でした。
松本駅――田沢―― 西条―― R143号― 青木峠
フキノトウ
緑の少ない今の時期ですが、登る途中で、ニワトコの芽吹き、
ヒカゲノカズラなどが見られました。
よく見かける蝶のさなぎ、 裸木や枯れ草の山では、目につきます。
何という蝶でしょうか。
ダンコウバイ 尾根や山頂で見かけました。
葉芽の展開に先駆けて、黄色い花を咲かせます。
茎を折り取ると、ツンとした香りが漂います。
山頂です。 曇り空のためはっきりしませんが、塩田平の田畑や
ため池が見えます。
お昼休みの後、下山します。
尾根の付近は広葉樹、マツタケの止め山もあります。
間伐して間もないため、林の中は見通しが良いのですが、
雑木などが少ないのは残念です。
登り口に、12:30到着です。
もう一山と、行きたいところですが、雨が降りそうなので
近くの大法寺を参拝します。
見返りの塔とも言われ
古くから親しまれているそうです。
シダレザクラが咲きはじめて
います。
境内には、赤いよだれかけの
六地蔵様、ユーモラスな
羅漢の石像、カヤの巨木、
足元の小さな草花など
心が和む風景に満ちています。
境内の梅林の向こうに、夫神山(オガミヤマ)が見えました。
今日登った子檀嶺岳(コマユミダケ)と、十観山(ジュッカンヤマ)で
青木村三山と言うそうです。 また、来たいと思います。
帰りは、田沢温泉の有乳湯(ウチユ)を楽しみます。
石畳の坂道に沿った、落ち着いた感じの温泉街です。
ぬるめのお湯に浸かって、ゆったりとくつろいで帰ります。
春の野菜畑
ようやく春本番の陽気になりました。
秋から育ててきた野菜を収穫したり、春の種まきなど忙しくなってきました。

初めて作った雪菜です。、和ガラシあえでいただきます。
ホウレンソウも、早く採らないとトウが立ってしまいます。
冬を越したラッキョウです。 右の写真のニンニクも作り方は同じです。


イチゴは、防寒と虫よけを兼ねてネットで覆ってみました。

よく見ると、1株に1~2個の白い花がついてます。
3月末に蒔いたエンドウも芽が出てきました。
よく似ていますが、グリンピースとスナップエンドウも芽が出てきています。


新しく借りた畑に、3日がかりで、ジャガイモを植えつけました。
左が植える前、右が植えつけた後で、7畝あります。


今年は、北あかり、メークイン、アンデスの3種類にしました。

これは、メークインの
種イモです。
芽の位置を見て、
3つくらいに切り分け
て、灰をつけて
みました。
ここまで済ませておけば、後の大部分の作業は5月の連休で良いと思います。
後は、草取りや芽かき・土寄せなどして、順調に育つようお天道さまにお任せです。
秋から育ててきた野菜を収穫したり、春の種まきなど忙しくなってきました。
初めて作った雪菜です。、和ガラシあえでいただきます。
ホウレンソウも、早く採らないとトウが立ってしまいます。
冬を越したラッキョウです。 右の写真のニンニクも作り方は同じです。
イチゴは、防寒と虫よけを兼ねてネットで覆ってみました。
よく見ると、1株に1~2個の白い花がついてます。
3月末に蒔いたエンドウも芽が出てきました。
よく似ていますが、グリンピースとスナップエンドウも芽が出てきています。
新しく借りた畑に、3日がかりで、ジャガイモを植えつけました。
左が植える前、右が植えつけた後で、7畝あります。
今年は、北あかり、メークイン、アンデスの3種類にしました。
これは、メークインの
種イモです。
芽の位置を見て、
3つくらいに切り分け
て、灰をつけて
みました。
ここまで済ませておけば、後の大部分の作業は5月の連休で良いと思います。
後は、草取りや芽かき・土寄せなどして、順調に育つようお天道さまにお任せです。

早春の岸辺にて
4月のある日、木曽川支流へ、友達と釣りに行きました。
天気は良いのですが、今日は魚の当たりはあまりありません。
流れをさかのぼって行くうち、いつのまにか、川岸へ目が向いていきます。
フクジュソウです。 休耕地が自然の原っぱに変わった場所に、花盛りです。
木曽地方のものは「ミチノクフクジュソウ」と言い、県北のものと少し違うのです。

小さなこの花、何と言ったかな~。 少しピンク色の花。
アズマイチゲ で良かったかな。
イチリンソウ? キクザキイチゲ? --- やはりアズマイチゲのようです。

湧き水の流れに、ワサビの株も花茎を伸ばし始めています。

裸木に、黄色の花が咲き始めています。 ジシャです。アブラチャンの
別名のとおり、枝を折り取ると、ツンとした香りが漂います。

ようやく、20センチほどのアマゴがきました。

この1匹で、今日の釣りは十分です。
のどかな春の水辺を、ブラブラ歩いて帰るのです。
天気は良いのですが、今日は魚の当たりはあまりありません。
流れをさかのぼって行くうち、いつのまにか、川岸へ目が向いていきます。
フクジュソウです。 休耕地が自然の原っぱに変わった場所に、花盛りです。
木曽地方のものは「ミチノクフクジュソウ」と言い、県北のものと少し違うのです。
小さなこの花、何と言ったかな~。 少しピンク色の花。
アズマイチゲ で良かったかな。
イチリンソウ? キクザキイチゲ? --- やはりアズマイチゲのようです。
湧き水の流れに、ワサビの株も花茎を伸ばし始めています。
裸木に、黄色の花が咲き始めています。 ジシャです。アブラチャンの
別名のとおり、枝を折り取ると、ツンとした香りが漂います。
ようやく、20センチほどのアマゴがきました。
この1匹で、今日の釣りは十分です。
のどかな春の水辺を、ブラブラ歩いて帰るのです。
スカイパークを歩く
2012年04月11日
リョウマ at 15:26
| Comments(2)
友達に誘われて、スカイパークを歩きました。
今週から、一気に春めいてきて、遠くの山々もおぼろげに霞んでいます。

(クリックして大きくしてね)
飛行場の吹き流しの向こうに、鉢盛山(2446m)が見えます。
かつては、八森山と言う字を当てたように樹木が多く茂る山だったそうです。
今は、朝日村からの登山道が荒れているようで、波田から登るのが良いようです。
いつも歩いている友達に,道順などを教えてもらいながら歩くのです。
10kmコースは、整備中ですが、青いセンターラインに沿って行けば良いのです。
コースでは、犬を連れた人・ゆっくり歩くお年寄り・ランニングの人などすれ違います。
ここは、両側がサクラ(ソメイヨシノ)です。花盛りにはさぞや見事な花のトンネルになるでしょう。

トサミズキの花がほころびかけています。

黄色い花木は、マンサクやジシャ(アブラチャン)なども目につきます。


紅梅が咲き始めています。
日差しを浴びた草地には、ホトケノザやオオイヌノフグりなどが、咲き競っています。
夏に、孫たちを連れて水遊びをしたことのある場所でハンカチの木を教わりました。
樹木の札には、 「ダビディア・ハンカチの木科・分布中国」 とあります。
白い花の咲く時期に、ぜひ見に来たいと思います。

この場所は、暖かくなると、岩山の奥から水が流れ出るのです。
ここの水が、水路に流れて子供たちの遊び場になるのです。
きれいな水ですので、地下水でも汲み上げているのでしょうか。
庭園風に芝を刈り込んだ場所があります。
葉の裏が白みをおびた、クリスマスツリーのような木が見えます。

樹木の札を見ると、「ピケアプンゲンス・トウヒの仲間・分布北アメリカ」 とあり、
ほかにも、メタセコイア(アケボニスギ)、ヒマラヤスギなどがあります。
こうして、1時間35分で、7,6kmを気持ち良く歩きました。
最初は、もう15分くらい早く着く予定で歩きだしたのですが、
写真を撮ったり・花を眺めたりと、見どころが多かったので、道草をくったのです。
お昼の時間になったので、二人で村井駅の方面に向かい、「西源の魚魚魚」で
「漁師飯」780円也を食べながら、次回に行く処などを相談しました。

漁師飯は、美味しく量も多いので値打ちでした。
今週から、一気に春めいてきて、遠くの山々もおぼろげに霞んでいます。
(クリックして大きくしてね)
飛行場の吹き流しの向こうに、鉢盛山(2446m)が見えます。
かつては、八森山と言う字を当てたように樹木が多く茂る山だったそうです。
今は、朝日村からの登山道が荒れているようで、波田から登るのが良いようです。
いつも歩いている友達に,道順などを教えてもらいながら歩くのです。
10kmコースは、整備中ですが、青いセンターラインに沿って行けば良いのです。
コースでは、犬を連れた人・ゆっくり歩くお年寄り・ランニングの人などすれ違います。
ここは、両側がサクラ(ソメイヨシノ)です。花盛りにはさぞや見事な花のトンネルになるでしょう。
トサミズキの花がほころびかけています。
黄色い花木は、マンサクやジシャ(アブラチャン)なども目につきます。
紅梅が咲き始めています。
日差しを浴びた草地には、ホトケノザやオオイヌノフグりなどが、咲き競っています。
夏に、孫たちを連れて水遊びをしたことのある場所でハンカチの木を教わりました。
樹木の札には、 「ダビディア・ハンカチの木科・分布中国」 とあります。
白い花の咲く時期に、ぜひ見に来たいと思います。
この場所は、暖かくなると、岩山の奥から水が流れ出るのです。
ここの水が、水路に流れて子供たちの遊び場になるのです。
きれいな水ですので、地下水でも汲み上げているのでしょうか。
庭園風に芝を刈り込んだ場所があります。
葉の裏が白みをおびた、クリスマスツリーのような木が見えます。
樹木の札を見ると、「ピケアプンゲンス・トウヒの仲間・分布北アメリカ」 とあり、
ほかにも、メタセコイア(アケボニスギ)、ヒマラヤスギなどがあります。
こうして、1時間35分で、7,6kmを気持ち良く歩きました。
最初は、もう15分くらい早く着く予定で歩きだしたのですが、
写真を撮ったり・花を眺めたりと、見どころが多かったので、道草をくったのです。
お昼の時間になったので、二人で村井駅の方面に向かい、「西源の魚魚魚」で
「漁師飯」780円也を食べながら、次回に行く処などを相談しました。

漁師飯は、美味しく量も多いので値打ちでした。

小谷村スノーシュー
友達に誘われて、 小谷村でのスノーシューに参加しました。
夜半からの雪降りで、柔らかな新雪を踏んで歩く一日となりました。
10:00 牛方宿からスタートです。
ここは、冬はお休みで、雪が軒先まで積もっています。
「青い旗」は主催のJAFさんのものです。

ここには、ずいぶん前、夏に来ただけで土地勘がありませんが、地元のガイドさんが案内してくれるのです。
まず、塩の道にもなっている、ノルディックのコースに沿って進み、帰りは山の尾根を歩くのです。

コースの途中で、ガイドさんが説明しているところです。
「頑張って歩けば、山頂でおいしいアメをごちそうします。」と期待させます。
雪に埋もれた百体観音を通過し、尾根を登って行くところです。
山中で、小学生ぐらいの子供達を交えた20名ほどのグループに会いました。
スキーを履いたり、ソリを持った元気なこどもたちです。

広い尾根を歩いて行く途中、雪の降るナラやモミジなどの林です。

(クリックして大きくしてね)
これは何でしょう?

山繭蛾(ヤママユガ)の蛹。 天蚕とも言うそうです。 ガイドさんが見せてくれました。
そして、お楽しみのアメと言うのは、「キハダを入れた水あめ・クロモジのお茶」でした。
両方とも山の幸です。
キハダの樹皮は百草丸の原料で苦いものですが、水あめに溶かしこんでほど良い香りと甘さ。
クロモジは、乾燥した枝を煎じたもので、やはり香りを楽しむのです。
こういう使い方もあることに、驚きました。
牛方宿まで戻って、午後から栂池ウッドチップロードの方へ行きます。
雪が本格的に降り出したため、約1時間に短縮したコースになりました。
途中で、ガイドさんから教わりました。

ツルマサキが広葉樹に巻きついて、ここだけが緑色に見えます。
次は、ミズキです。枝が水平に広がり、白い細かな花がつく木です。

この枝に、米粉の「マユダマ」を刺して、ドンド焼きに使うそうです。
(うちの方では、柳の枝を使うことが多いです。)
カモシカに出会うことを期待し、親沢川の崖上まで進みました。
カモシカには会えませんでしたが、なぜか、みんな前方を見つめています。

少しだけど、陽が射して白馬村との境界にある山が見えたのです。
(山の名前は忘れましたけど。)

はっきりしませんが、山並みは分かりますので、クリックしてみてください。
こうして、3時間ほどのスノーシューでしたが、新雪を存分に楽しむことができ
感謝です。
JAFさん・村のガイドさんたち お世話になり、ありがとうございました。
夜半からの雪降りで、柔らかな新雪を踏んで歩く一日となりました。

10:00 牛方宿からスタートです。
ここは、冬はお休みで、雪が軒先まで積もっています。
「青い旗」は主催のJAFさんのものです。
ここには、ずいぶん前、夏に来ただけで土地勘がありませんが、地元のガイドさんが案内してくれるのです。
まず、塩の道にもなっている、ノルディックのコースに沿って進み、帰りは山の尾根を歩くのです。
コースの途中で、ガイドさんが説明しているところです。
「頑張って歩けば、山頂でおいしいアメをごちそうします。」と期待させます。
雪に埋もれた百体観音を通過し、尾根を登って行くところです。
山中で、小学生ぐらいの子供達を交えた20名ほどのグループに会いました。
スキーを履いたり、ソリを持った元気なこどもたちです。
広い尾根を歩いて行く途中、雪の降るナラやモミジなどの林です。
(クリックして大きくしてね)
これは何でしょう?
山繭蛾(ヤママユガ)の蛹。 天蚕とも言うそうです。 ガイドさんが見せてくれました。
そして、お楽しみのアメと言うのは、「キハダを入れた水あめ・クロモジのお茶」でした。
両方とも山の幸です。
キハダの樹皮は百草丸の原料で苦いものですが、水あめに溶かしこんでほど良い香りと甘さ。
クロモジは、乾燥した枝を煎じたもので、やはり香りを楽しむのです。
こういう使い方もあることに、驚きました。
牛方宿まで戻って、午後から栂池ウッドチップロードの方へ行きます。
雪が本格的に降り出したため、約1時間に短縮したコースになりました。
途中で、ガイドさんから教わりました。
ツルマサキが広葉樹に巻きついて、ここだけが緑色に見えます。
次は、ミズキです。枝が水平に広がり、白い細かな花がつく木です。
この枝に、米粉の「マユダマ」を刺して、ドンド焼きに使うそうです。
(うちの方では、柳の枝を使うことが多いです。)
カモシカに出会うことを期待し、親沢川の崖上まで進みました。
カモシカには会えませんでしたが、なぜか、みんな前方を見つめています。
少しだけど、陽が射して白馬村との境界にある山が見えたのです。
(山の名前は忘れましたけど。)
はっきりしませんが、山並みは分かりますので、クリックしてみてください。
こうして、3時間ほどのスノーシューでしたが、新雪を存分に楽しむことができ
感謝です。
JAFさん・村のガイドさんたち お世話になり、ありがとうございました。
穂高岳と山賊焼き
塩尻の良いところは、穂高岳の眺めと名物の山賊焼きです。
最初は、駅の近く「ホテル中村屋」の屋上からの穂高岳です。
直線距離で、約35kmです。

(クリックして大きくしてね。)
ついでに同じ中村屋から、塩尻峠の向こうに広がる八ヶ岳です。
直線距離で、約42kmです。

(クリックして大きくしてね。)
お天気の良い日は、市内のいろいろな場所から、眺めを楽しめるのです。
これは、道の駅「小坂田」からの穂高岳です。

この日も、天気が良かったので、ここでの待ち合わせの時間を利用して、
パチリです。
ホテル中村屋での会合の時、名物の「山賊焼き」を食べました。
こんな感じです。 ボリュームがあって、美味しいのです。

塩尻っ子の集いだったので、話が弾みます。
「元祖山賊焼き」では、最初の頃お酒2杯かビールを飲まないと、山賊を注文できなかった。
---- それは、最初は、ひねっ鶏を買い集めて、出していたから品物が間に合わなかったせいだよ。
高速の「みどり湖パーキング」の山賊は、以前市内にあった「夕月」の味を引き継いでいるから美味しいよ。
---- 高速の外に、車を止めて買いにいけばいいよ。
---- 「五千石」や「桔梗」の山賊もいいよ。
若いころ、「海賊」というのもあったね。
---- そうそう、山賊とは少し違った感じで、やはり美味しかったね。
などなど、話題は尽きないのです。

ホテルの前にある「元祖 山賊焼き」の石碑です。
先代が建てたそうです。
最初は、駅の近く「ホテル中村屋」の屋上からの穂高岳です。
直線距離で、約35kmです。

(クリックして大きくしてね。)
ついでに同じ中村屋から、塩尻峠の向こうに広がる八ヶ岳です。
直線距離で、約42kmです。

(クリックして大きくしてね。)
お天気の良い日は、市内のいろいろな場所から、眺めを楽しめるのです。
これは、道の駅「小坂田」からの穂高岳です。

この日も、天気が良かったので、ここでの待ち合わせの時間を利用して、
パチリです。
ホテル中村屋での会合の時、名物の「山賊焼き」を食べました。
こんな感じです。 ボリュームがあって、美味しいのです。

塩尻っ子の集いだったので、話が弾みます。
「元祖山賊焼き」では、最初の頃お酒2杯かビールを飲まないと、山賊を注文できなかった。
---- それは、最初は、ひねっ鶏を買い集めて、出していたから品物が間に合わなかったせいだよ。
高速の「みどり湖パーキング」の山賊は、以前市内にあった「夕月」の味を引き継いでいるから美味しいよ。
---- 高速の外に、車を止めて買いにいけばいいよ。
---- 「五千石」や「桔梗」の山賊もいいよ。
若いころ、「海賊」というのもあったね。
---- そうそう、山賊とは少し違った感じで、やはり美味しかったね。
などなど、話題は尽きないのです。

ホテルの前にある「元祖 山賊焼き」の石碑です。
先代が建てたそうです。
霧ヶ峰スノーシュー
今シーズン2回目のスノーシューです。
快晴とは言えませんが、まずますの天気です。
10:10 沢渡(サワワタリ)をスタートです。

太陽が傘をかぶったよう。
ウサギなど小動物の足跡やミズナラ・コナシなどの冬景色の中、
緩やかな登りを一歩ずつ進みます。

11:00 車山肩の 「ころぼっくるヒュッテ」 (1920m)付近です。
来た道を振り返ると、鷲ヶ峰と三峯山の手前に、八島ヶ原湿原1632mです。
背景に、御岳から乗鞍北アルプスが遠望できます。
遠くてはっきりしませんが、三峯山と美ヶ原の間に鹿島槍ヶ岳が見えるのです。

(クリックして大きくしてね。)
「霧ケ峰湿原」を通ります。 植物保護のため、歩く道は柵の内です。
雪の下は木道になっているようです。
レンゲツツジが多く6月頃に来てみたい場所です。

蝶々深山(1836m)
12:00です。このまま少し歩いて、
風当たりの弱いところで昼食にします。

ウサギの足跡です。

やや雪の深いところに
ありました。
実際にウサギなどの小動物
を目にすることはほとんど
ありませんが、
雪には、こうした発見の
楽しみもありますね。
シカの食害です。
カラマツの幹を齧ってあります。
湿原の周囲には柵を巡らせてありますが、シカが2頭入ってしまったそうです。
雪解けのとき、貴重な植物が食べられずにすむ方策があるのでしょうか。

桟敷の跡です。
古い時代に、武技を競って奉納する場面を見た、ひな壇の跡が、
段々になっています。
この霧ケ峰は、草刈りなど、古くから人の手が入っているのです。

県史跡の看板です

(クリックして大きくしてね。)
八島ケ原湿原 13:15
沢渡 帰着 13:45
約3時間半の行程でした。
本日の歩行数 11,000歩
最後に、片倉館で入浴。ゆっくり楽しめた一日でした。
快晴とは言えませんが、まずますの天気です。

10:10 沢渡(サワワタリ)をスタートです。
太陽が傘をかぶったよう。
ウサギなど小動物の足跡やミズナラ・コナシなどの冬景色の中、
緩やかな登りを一歩ずつ進みます。
11:00 車山肩の 「ころぼっくるヒュッテ」 (1920m)付近です。
来た道を振り返ると、鷲ヶ峰と三峯山の手前に、八島ヶ原湿原1632mです。
背景に、御岳から乗鞍北アルプスが遠望できます。
遠くてはっきりしませんが、三峯山と美ヶ原の間に鹿島槍ヶ岳が見えるのです。

(クリックして大きくしてね。)
「霧ケ峰湿原」を通ります。 植物保護のため、歩く道は柵の内です。
雪の下は木道になっているようです。
レンゲツツジが多く6月頃に来てみたい場所です。
蝶々深山(1836m)
12:00です。このまま少し歩いて、
風当たりの弱いところで昼食にします。
ウサギの足跡です。
やや雪の深いところに
ありました。
実際にウサギなどの小動物
を目にすることはほとんど
ありませんが、
雪には、こうした発見の
楽しみもありますね。
シカの食害です。
カラマツの幹を齧ってあります。
湿原の周囲には柵を巡らせてありますが、シカが2頭入ってしまったそうです。
雪解けのとき、貴重な植物が食べられずにすむ方策があるのでしょうか。
桟敷の跡です。
古い時代に、武技を競って奉納する場面を見た、ひな壇の跡が、
段々になっています。
この霧ケ峰は、草刈りなど、古くから人の手が入っているのです。

県史跡の看板です

(クリックして大きくしてね。)
八島ケ原湿原 13:15
沢渡 帰着 13:45
約3時間半の行程でした。
本日の歩行数 11,000歩
最後に、片倉館で入浴。ゆっくり楽しめた一日でした。

渓流釣りの解禁
木曽川水系の渓流釣りが解禁になりました。
友達と待ち合わせて、木曽川の支流に7時到着です。
前日の雪で、川岸や田畑には積雪がありますが、今日は暖かくなりそうです。
最初のポイントには、すでに二人の釣り人が見えます。
上流へ車を進め、入渓します。
ここはまだ誰も歩いていないようです。
友達と交互に、上流へ釣っていきます。
まだ水量が少ないです。 雪解け水が出て魚が活発に泳ぐようになれば、
本当のシーズン到来です。

今日は、餌釣りです。 深いところを選んで仕掛けを投入します。
最初の当たりです。
 イワナです。
イワナです。
25cmほどで白い斑点。
ニッコウイワナ
放流ものです。
とりあえず、
1匹釣れ、ホッとします。
友達も、堰堤の下の深みで、1匹あげました。
「アマゴ」と、言ってます。
少し上流の堰堤下で、竿を出します。
コツコツの当たりの後、仕掛けが引き込まれます。
型の良い、オレンジの斑点があるイワナです。
木曽川在来種のヤマトイワナです。

(クリックして大きくしてね。)
続いてアマゴです。
木曽の人は、タナビラと言い、美味しい魚です。
まだ、冬のサビが取れていませんが、この川で育ったアマゴで、
尾びれのオレンジ色が鮮やかです。

(クリックして大きくしてね。)
この堰堤で釣れたのです。
今の時期は、まだこうした深みにいるのです。

友達も、頑張って釣っています。

その後、漁協の人に会ったので、話を聞きました。
「アマゴは、去年6月に稚魚を放したもので、本流には、アマゴの成魚を放流してある。」
とのこと。 エサが多いのか、良く育っていると思います。
途中から、他の釣り人の足跡が目につくようになったので、場所を変えました。

こちらの川も、水量は少なめですが、魚影が濃い感じで、楽しめそうです。
ポイントではいい反応があり、アマゴが少し大き目です。
樹木に覆われている淵で、緩やかな流れの上を羽虫が飛び交っています。
竿を出さずにしばらく見ていると、水面にモジリが現れたり、飛沫が上がります。
ハッチしているカゲロウを、魚が捕食しているのです。 驚きました。
今日は暖かいからでしょうか。
解禁の時期に、思いがけない光景に出合いました。
しばらく釣りあがり、釣果も10匹ほどになったところで、早めですが納竿としました。
この次の釣行は、川の水が温んで、「フキノトウ」が開くころになるでしょう。
友達と待ち合わせて、木曽川の支流に7時到着です。
前日の雪で、川岸や田畑には積雪がありますが、今日は暖かくなりそうです。
最初のポイントには、すでに二人の釣り人が見えます。
上流へ車を進め、入渓します。
ここはまだ誰も歩いていないようです。
友達と交互に、上流へ釣っていきます。
まだ水量が少ないです。 雪解け水が出て魚が活発に泳ぐようになれば、
本当のシーズン到来です。
今日は、餌釣りです。 深いところを選んで仕掛けを投入します。
最初の当たりです。
25cmほどで白い斑点。
ニッコウイワナ
放流ものです。
とりあえず、
1匹釣れ、ホッとします。

友達も、堰堤の下の深みで、1匹あげました。
「アマゴ」と、言ってます。
少し上流の堰堤下で、竿を出します。
コツコツの当たりの後、仕掛けが引き込まれます。
型の良い、オレンジの斑点があるイワナです。
木曽川在来種のヤマトイワナです。
(クリックして大きくしてね。)
続いてアマゴです。
木曽の人は、タナビラと言い、美味しい魚です。
まだ、冬のサビが取れていませんが、この川で育ったアマゴで、
尾びれのオレンジ色が鮮やかです。
(クリックして大きくしてね。)
この堰堤で釣れたのです。
今の時期は、まだこうした深みにいるのです。
友達も、頑張って釣っています。
その後、漁協の人に会ったので、話を聞きました。
「アマゴは、去年6月に稚魚を放したもので、本流には、アマゴの成魚を放流してある。」
とのこと。 エサが多いのか、良く育っていると思います。
途中から、他の釣り人の足跡が目につくようになったので、場所を変えました。
こちらの川も、水量は少なめですが、魚影が濃い感じで、楽しめそうです。
ポイントではいい反応があり、アマゴが少し大き目です。
樹木に覆われている淵で、緩やかな流れの上を羽虫が飛び交っています。
竿を出さずにしばらく見ていると、水面にモジリが現れたり、飛沫が上がります。
ハッチしているカゲロウを、魚が捕食しているのです。 驚きました。

今日は暖かいからでしょうか。
解禁の時期に、思いがけない光景に出合いました。
しばらく釣りあがり、釣果も10匹ほどになったところで、早めですが納竿としました。
この次の釣行は、川の水が温んで、「フキノトウ」が開くころになるでしょう。
安曇野から見る北アルプス
よく晴れた冬の一日、「山を見に行こう。」と家内が言うので、安曇野へ出かけた。
最初は、「堀金道の駅」の近く、十ケ堰の流れに沿って。

田園の向こう、西北に白馬方面の山が見えるが、まだ少し雲がかかっている。
真北の方向にも、白い山が見える。
 (クリックして大きくしてね。)
(クリックして大きくしてね。)
あれは何と言う山なんだろう。
妙高山に似ている、それとも雨飾山か?
「堀金道の駅」を覗いた、ここの食堂のメニュ―は美味しそう。
でも、お昼には早すぎます。
先を急いで、穂高で有明山(2268m)をパチリと一枚。
散歩中のご婦人と、家内が話してます。「有明山の左が燕岳だよ。」教えていただく。

山がよく見えるうちに、もっと近づこうと車を山麓へ走らすが.-------
不思議、ふしぎ、反って遠くに離れていくようだ。
もう一度、下に下りる。北へ向かうと、「アルプス展望ロード」の看板だ。
乳川の近くに良い場所があった。 ヨシ、ここだ。
乳川の岸辺が、遊歩道になっている。 松川村細野地区です。


ここでパチリ。(クリックして大きくしてね。)
左の写真が、蓮華岳(2799m)です。
右の写真が、爺ケ岳(2670m) ・鹿島槍ケ岳(2889m)
五龍岳(2814m)・白馬岳(2932m)です。
雪形の現れるころ、もっと近くで、白馬村まで行って撮りたい山です。
穂高の大王わさび農場の付近で。
少し遠いですが、蓮華岳~白馬岳まで入っています。

(クリックしてね。)
帰り道、常念岳(2857m)を撮ってみました。
左が、先ほどのわさび農場・右が南に移動した子供病院の近くです。



最初は、「堀金道の駅」の近く、十ケ堰の流れに沿って。

田園の向こう、西北に白馬方面の山が見えるが、まだ少し雲がかかっている。
真北の方向にも、白い山が見える。
 (クリックして大きくしてね。)
(クリックして大きくしてね。)あれは何と言う山なんだろう。
妙高山に似ている、それとも雨飾山か?
「堀金道の駅」を覗いた、ここの食堂のメニュ―は美味しそう。
でも、お昼には早すぎます。
先を急いで、穂高で有明山(2268m)をパチリと一枚。
散歩中のご婦人と、家内が話してます。「有明山の左が燕岳だよ。」教えていただく。

山がよく見えるうちに、もっと近づこうと車を山麓へ走らすが.-------
不思議、ふしぎ、反って遠くに離れていくようだ。
もう一度、下に下りる。北へ向かうと、「アルプス展望ロード」の看板だ。
乳川の近くに良い場所があった。 ヨシ、ここだ。

乳川の岸辺が、遊歩道になっている。 松川村細野地区です。


ここでパチリ。(クリックして大きくしてね。)
左の写真が、蓮華岳(2799m)です。
右の写真が、爺ケ岳(2670m) ・鹿島槍ケ岳(2889m)
五龍岳(2814m)・白馬岳(2932m)です。
雪形の現れるころ、もっと近くで、白馬村まで行って撮りたい山です。
穂高の大王わさび農場の付近で。
少し遠いですが、蓮華岳~白馬岳まで入っています。

(クリックしてね。)
帰り道、常念岳(2857m)を撮ってみました。
左が、先ほどのわさび農場・右が南に移動した子供病院の近くです。


夏の思い出 ①
「ユウ君が、夏休みの自由研究で川の生き物を調べるから、お願いね。」 と、娘から頼まれた。
「お得意の分野だからいいでしょう。」 と、おまけの一言もあって張り切らざるをえない。
小3の妹も連れて、とりあえず、近くの田川に行ってみることにした。
最初は 大正橋の下流で、川に下りやすい処を探して。
生き物は、細かい目の手網で捕って、バケツに入れて。
デジカメで撮るときには、納豆の空いたケースで。
写真に撮ったら、逃がしてやる。
水際の草むらをガサガサして、手網をあげると。---
ドジョウです。

お次は、 アブラハヤかウグイの幼魚です。
小さすぎて、どちらか分かりません。


ちょっと気持ちの悪いヘビトンボの幼虫です。
この鋭いハサミで何を食べているのでしょう。
ハグロトンボ(オス)です。 メスは 羽の先に白い点の模様です。


これは、ハグロトンボの幼虫です。 なんとなく成虫の形に似ています。

シジミとカワニナです。
どちらも、貝殻の状態で中身は入って
いなくてとても小さいのです。
でも、シジミが田川にいると言うことが
貴重なのです。
図鑑で見ると、マシジミと言い、
食用に売っている汽水域のものとは違う
種類なのです。なんとか、生息している
ところを探したいと思い、こちらが夢中に
なってしまいます。
これは、クロカワムシ 釣りのエサに良いのです。
本当の名前は、ヒゲナガトビケラでした。

「お得意の分野だからいいでしょう。」 と、おまけの一言もあって張り切らざるをえない。
小3の妹も連れて、とりあえず、近くの田川に行ってみることにした。
最初は 大正橋の下流で、川に下りやすい処を探して。
生き物は、細かい目の手網で捕って、バケツに入れて。
デジカメで撮るときには、納豆の空いたケースで。
写真に撮ったら、逃がしてやる。
水際の草むらをガサガサして、手網をあげると。---
ドジョウです。
お次は、 アブラハヤかウグイの幼魚です。
小さすぎて、どちらか分かりません。
この鋭いハサミで何を食べているのでしょう。
ハグロトンボ(オス)です。 メスは 羽の先に白い点の模様です。
これは、ハグロトンボの幼虫です。 なんとなく成虫の形に似ています。
シジミとカワニナです。
どちらも、貝殻の状態で中身は入って
いなくてとても小さいのです。
でも、シジミが田川にいると言うことが
貴重なのです。
図鑑で見ると、マシジミと言い、
食用に売っている汽水域のものとは違う
種類なのです。なんとか、生息している
ところを探したいと思い、こちらが夢中に
なってしまいます。
これは、クロカワムシ 釣りのエサに良いのです。
本当の名前は、ヒゲナガトビケラでした。
そのほかにも、この田川にはホタルがいて、6月下旬にはゲンジボタル
7月にはヘイケボタルが見られ、地元の人たちは、大切にしているのです。
子供用の釣り場には、漁協で小型のニジマスを放流し、ヤマメもいるのです。
小学生でも釣りを楽しめる場所を用意してあるのです。
それでも、私たちの子供のころとは、川の姿は大きく変わりました。
コンクリートで護岸され、川に下りることも難しいので、
大人がついて行かないと危ないのです。
それに、年中 カワウやサギ類に攻められて、産卵できる大きさの魚は
ほんとうに少ないのです。
そんな環境でも、いつの間にか生き物たちが復活していることに
驚かされるのです。
ささやかな自然ですが、いつまでも魚や虫たちの棲家でいてほしいです。
7月にはヘイケボタルが見られ、地元の人たちは、大切にしているのです。
子供用の釣り場には、漁協で小型のニジマスを放流し、ヤマメもいるのです。
小学生でも釣りを楽しめる場所を用意してあるのです。
それでも、私たちの子供のころとは、川の姿は大きく変わりました。
コンクリートで護岸され、川に下りることも難しいので、
大人がついて行かないと危ないのです。
それに、年中 カワウやサギ類に攻められて、産卵できる大きさの魚は
ほんとうに少ないのです。
そんな環境でも、いつの間にか生き物たちが復活していることに
驚かされるのです。
ささやかな自然ですが、いつまでも魚や虫たちの棲家でいてほしいです。
夏の思い出 ②
小学生を対象にした「奈良井川探検隊」と言う催しがありました。
小4のユウ君と妹に、私は保護者ということで参加しました。
最初に連れて行ってもらった場所は、小曽部川の上流です。
流れの脇を林道が通っていて、川に入りやすく、
夏のため水量は少なめですが、きれいに澄んでいます。
この辺りは、禁漁区です。 秋のキノコとりの頃には、
産卵前の大きなイワナを見ることもできるところです。

さっそく、川に入って手網で流れの中をジャブジャブします。
どの子も、生き生きと動き回っています。

ヤゴです。 これはコオニヤンマのヤゴです。

大きなカワゲラ イワナ釣りに良い餌です。

カワゲラの右下のヒルみたいなものは、
ウズムシと言い、きれいな流れにだけ
棲息しているそうです。
羽化したばかりのカワゲラの成虫が止まっています。
羽がまだ柔らかな感じです。

奈良井川に移動してから、ーーーー
飛んできたオニヤンマを、ユウ君がすばやく捕まえたのです。

そして、夏休みの終わりの頃です。
もう一度、3人で奈良井川に行ってみました。
サワガニとドジョウです。本流の脇、浅いところの石の下にいました。

雨が降ってきたので、帰ろうと車に乗ると、虹です。
東の空に架かる虹を追いかけるようにして、家路をたどります。
家へ着いたら、向かいの家の屋根の上にくっきりと出ています。

「ただいま~ お母さん にじがきれいだよ。」
玄関で、子供たちの声が弾みます。
小4のユウ君と妹に、私は保護者ということで参加しました。
最初に連れて行ってもらった場所は、小曽部川の上流です。
流れの脇を林道が通っていて、川に入りやすく、
夏のため水量は少なめですが、きれいに澄んでいます。
この辺りは、禁漁区です。 秋のキノコとりの頃には、
産卵前の大きなイワナを見ることもできるところです。
さっそく、川に入って手網で流れの中をジャブジャブします。
どの子も、生き生きと動き回っています。
ヤゴです。 これはコオニヤンマのヤゴです。
大きなカワゲラ イワナ釣りに良い餌です。
カワゲラの右下のヒルみたいなものは、
ウズムシと言い、きれいな流れにだけ
棲息しているそうです。
羽化したばかりのカワゲラの成虫が止まっています。
羽がまだ柔らかな感じです。
奈良井川に移動してから、ーーーー
飛んできたオニヤンマを、ユウ君がすばやく捕まえたのです。

そして、夏休みの終わりの頃です。
もう一度、3人で奈良井川に行ってみました。
サワガニとドジョウです。本流の脇、浅いところの石の下にいました。
雨が降ってきたので、帰ろうと車に乗ると、虹です。

東の空に架かる虹を追いかけるようにして、家路をたどります。
家へ着いたら、向かいの家の屋根の上にくっきりと出ています。
「ただいま~ お母さん にじがきれいだよ。」
玄関で、子供たちの声が弾みます。
八ヶ岳をスノーシューで
八ヶ岳をスノーシューで歩こう。
ベテランのリーダーに引率された、いつものメンバーでの山行です。
9:40 ピラタス蓼科ロープウェイに乗車ーー 10:00 山頂駅
スキーゲレンデの向こうは、蓼科山です。
ロープウェイの中からは遠くの南アルプス・中央アルプス・御岳山・
北アルプスが よく見え、絶好の登山日和です。

山頂駅(2,237m)から、スノーシューを着けて出発。
今日一日は、天気が良いとの予報なので、縞枯山へ足を延ばす
ことになりました。

まもなく、縞枯山荘が見えてきました。
山荘の前は、雪原になっていますが、雪のない時は、湿原らしく立ち入り禁止です。

登山道は、スノーシューには勾配の急な直登の道でしたが、
思ったより早く、稜線が明るくなっているのが分かり、楽に登れた感じです。
11:10 縞枯山(2403m)の稜線に到着です。

展望台からは、南八ヶ岳の 編笠岳・赤岳・阿弥陀岳などの峰々がみえます。
稜線のシラビソなどの樹木は枯れていますが、次の世代が育っています。

茶臼山方面に下り、五辻を経由して、ロープウェイの駅まで戻る途中、
樹木へのシカの食み跡が目につきます。 この新しい傷は今冬のもので、
薄い形成層をぐるりと食べられると、木は枯れるのです。沢山の食み跡を見る
と増えすぎたシカを間引く必要があると感じるのです。

そうは言いながら、車での帰途に、道路を横切ろうと雪の林中で待っていた
シカの可愛い姿に感動させられたりもするのです。
途中で、今日の目的地「北横岳」の山並みが見えます。

五辻で昼食をとり、ロープウェイ駅へ着いたのが、13:30でした。

山頂駅からは、スキーヤー達が次々とコースへ出ていきます。
縞枯山周辺の案内板です。

いよいよ、坪庭を経由して北横岳へ向かいます。
岩石と盆栽のような樹木が坪庭のような広がりを見せるのです。

登りにかかり、熟年の男女ペアとすれちがいました。
アイゼンを着けています。 慣れているらしく、足早に下っていきます。

15:20 北横岳ヒュッテ(2400m 40人収容)に到着です。
明日は雪降りになりそうですから、休まず山頂に行ってきます。

シラビソの樹林帯を登ります。この辺りは、積雪量が多いようです。

北横岳(2480m)の南峰・北峰に行きました。
もう雪が降りだして、眺望が効きませんが、今日のうちに来てよかったです。
これは、岩の隙間から吹き出す風が凍った 結晶 だそうです。
登山道の脇にありました。

16:30 北横岳ヒュッテ到着 今日の歩行数は16、000歩でした。
薪ストーブの周りで、ヒュッテのオーナーも加わり、
ビール・コーヒー・持ち寄りのつまみで、ゆっくり談笑します。
オーナーの写真ブックを見せてもらったり、楽しいひとときでした。
続きを読む
ベテランのリーダーに引率された、いつものメンバーでの山行です。
9:40 ピラタス蓼科ロープウェイに乗車ーー 10:00 山頂駅
スキーゲレンデの向こうは、蓼科山です。
ロープウェイの中からは遠くの南アルプス・中央アルプス・御岳山・
北アルプスが よく見え、絶好の登山日和です。

山頂駅(2,237m)から、スノーシューを着けて出発。
今日一日は、天気が良いとの予報なので、縞枯山へ足を延ばす
ことになりました。
まもなく、縞枯山荘が見えてきました。
山荘の前は、雪原になっていますが、雪のない時は、湿原らしく立ち入り禁止です。
登山道は、スノーシューには勾配の急な直登の道でしたが、
思ったより早く、稜線が明るくなっているのが分かり、楽に登れた感じです。
11:10 縞枯山(2403m)の稜線に到着です。
展望台からは、南八ヶ岳の 編笠岳・赤岳・阿弥陀岳などの峰々がみえます。
稜線のシラビソなどの樹木は枯れていますが、次の世代が育っています。
茶臼山方面に下り、五辻を経由して、ロープウェイの駅まで戻る途中、
樹木へのシカの食み跡が目につきます。 この新しい傷は今冬のもので、
薄い形成層をぐるりと食べられると、木は枯れるのです。沢山の食み跡を見る
と増えすぎたシカを間引く必要があると感じるのです。
そうは言いながら、車での帰途に、道路を横切ろうと雪の林中で待っていた
シカの可愛い姿に感動させられたりもするのです。
途中で、今日の目的地「北横岳」の山並みが見えます。
五辻で昼食をとり、ロープウェイ駅へ着いたのが、13:30でした。
山頂駅からは、スキーヤー達が次々とコースへ出ていきます。
縞枯山周辺の案内板です。
いよいよ、坪庭を経由して北横岳へ向かいます。
岩石と盆栽のような樹木が坪庭のような広がりを見せるのです。
登りにかかり、熟年の男女ペアとすれちがいました。
アイゼンを着けています。 慣れているらしく、足早に下っていきます。
15:20 北横岳ヒュッテ(2400m 40人収容)に到着です。
明日は雪降りになりそうですから、休まず山頂に行ってきます。
シラビソの樹林帯を登ります。この辺りは、積雪量が多いようです。
北横岳(2480m)の南峰・北峰に行きました。
もう雪が降りだして、眺望が効きませんが、今日のうちに来てよかったです。

これは、岩の隙間から吹き出す風が凍った 結晶 だそうです。
登山道の脇にありました。
16:30 北横岳ヒュッテ到着 今日の歩行数は16、000歩でした。
薪ストーブの周りで、ヒュッテのオーナーも加わり、
ビール・コーヒー・持ち寄りのつまみで、ゆっくり談笑します。
オーナーの写真ブックを見せてもらったり、楽しいひとときでした。

続きを読む
手打ちほうとう
そば打ちの番外編として、「ほうとう」をつくりました。
最初は、手打ちうどんを作るつもりで始めたのですが ーーーーー。
分量は、地粉500gに、水225cc、塩25gです。
鉢の中で、手で大体の塊にしてから、ビニールの袋に入れて、足で踏みます。
3時間ほど、布団の中でねかせてから、のし棒でのばします。
包丁で切るのですが、そばとは違って大体でいいのです。

切り口がくっつかないよう、コーンスターチをまぶします。

でも、切り方がいいかげんだったので、平たくて「ほうとう」みたいです。
家内が、「ほうとうも、おいしそうだから、変更しましょう。」と
ここで、ほうとうづくりになりました。
ここからは、家内の出番です。

カボチャ、ニンジン、キノコ、ハクサイ、サトイモ、ナガネギなど家にある野菜と肉・油あげが少々です。

野菜などが煮えてきたら、「うどん」 いいえ、「ほうとう」を入れます。
最後に、味噌で味をつけてーーーー。
続きを読む
最初は、手打ちうどんを作るつもりで始めたのですが ーーーーー。
分量は、地粉500gに、水225cc、塩25gです。
鉢の中で、手で大体の塊にしてから、ビニールの袋に入れて、足で踏みます。
3時間ほど、布団の中でねかせてから、のし棒でのばします。
包丁で切るのですが、そばとは違って大体でいいのです。
切り口がくっつかないよう、コーンスターチをまぶします。
でも、切り方がいいかげんだったので、平たくて「ほうとう」みたいです。
家内が、「ほうとうも、おいしそうだから、変更しましょう。」と
ここで、ほうとうづくりになりました。
ここからは、家内の出番です。
カボチャ、ニンジン、キノコ、ハクサイ、サトイモ、ナガネギなど家にある野菜と肉・油あげが少々です。
野菜などが煮えてきたら、「うどん」 いいえ、「ほうとう」を入れます。
最後に、味噌で味をつけてーーーー。
続きを読む
冬の山
今日は、久しぶりに山がよく見えました。 自転車で写真の撮れそうな場所を探します。
最初は、国道19号の歩道橋から「穂高連峰」です。

まだ少し雲がありますが、なんとか写っています。
次は塩尻駅の西口の南から、「八ヶ岳」です。

(写真をクリックしてね。少しだけど大きくなるよ)
最初は、国道19号の歩道橋から「穂高連峰」です。

まだ少し雲がありますが、なんとか写っています。
次は塩尻駅の西口の南から、「八ヶ岳」です。

(写真をクリックしてね。少しだけど大きくなるよ)
寒い朝
この冬一番の冷え込みです。
氷点下10度C以下にはなったと思います。
情報プラザへ行く途中、穂高連峰がきれいに見えました。
今度は、カメラ持参で出かけましょう。
氷点下10度C以下にはなったと思います。
情報プラザへ行く途中、穂高連峰がきれいに見えました。
今度は、カメラ持参で出かけましょう。